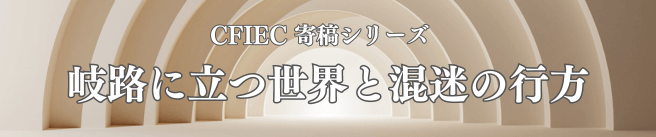
75周年を迎えたNATOの苦悩
―ウクライナ、ロシア、トランプ
―ウクライナ、ロシア、トランプ

掲載日:2024年4月18日
慶應義塾大学総合政策学部 准教授
鶴岡 路人
1949年4月4日の北大西洋条約(ワシントン条約)署名から75年がたった。国家間の同盟が同じ基本条約のまま75周年を迎える事例はそれほど多くない。NATO(北大西洋条約機構)は、「史上最も成功した同盟」と呼ばれることも多い。
しかし、どれだけ成功していると考えるかは期待値次第でもある。全加盟国が一糸乱れぬ結束を常に維持していることが当然だという前提に立てば、現実のNATOはばらばらであり、低い評価をせざるをえない。他方、加盟各国の歴史や地理的条件が異なる以上、立場が一致しないのが当然だと考えれば、現実のNATOは期待以上という評価になるだろう。
NATOは、加盟国間の対立や同盟全体の危機の歴史としてみることも可能であれば、異なる立場を乗り越えてきた歴史だと捉えることもできる。どちらも真実である。そのうえでなお、今日のNATOは深刻な課題を抱えている。まさに苦悩する同盟だ。主なものは、継続的なウクライナ支援をいかに確保するのか、ロシアが「勝利」してしまった場合に欧州の安全保障をどのように維持するのか、そして米国の欧州への関与が本質的に弱まった場合にどう対応するのかの3つである。順にみていくことにしよう。
ウクライナ支援をいかに継続するか
2022年2月にはじまったロシアによるウクライナ全面侵攻に関して、NATOの最大の役割は加盟国の防衛であり、そのための対露抑止・防衛態勢の強化である。この点は重要で、同盟の観点では、ウクライナ支援が最重要課題なのではない。そして実際、バルト諸国やポーランドをはじめとして、ロシアやウクライナと国境を接するNATO加盟国の防衛強化のために、米国やその他諸国の部隊が派遣されている。
そのうえでNATOは、早期警戒管制機(AWACS)を主にポーランド上空などに飛ばし、そこからウクライナ領内を含めたロシアの航空機やミサイルを監視してきた。この情報の一部はウクライナにも提供されてきたといわれる。また、NATOの基金を通じて非殺傷兵器のウクライナへの供与が実施されてきた。加えて、50カ国以上にのぼるウクライナへの武器供与国の枠組みとして米国主導で開催されてきたウクライナ防衛コンタクトグループ(Ukraine Defense Contact Group:いわゆる「ラムシュタイン会合」)に関与し、ときに会合場所を提供してきたのがNATOである。
ただし、ウクライナへの殺傷武器の供与はウクライナとの二国間の合意に基づき各国が独自に実施してきた。ラムシュタイン会合では、ウクライナ側の要望を踏まえ、各国による供与内容の調整がおこなわれるが、最終的な判断を下すのは各国政府であるし、国によっては供与内容の詳細を発表しないこともある。その背後にはさまざまな事情が存在する。一部諸国ではロシアを刺激したくないという考慮がいまだに存在するし、また例えば供与する砲弾やミサイルの数を発表してしまっては、供与国側の残りの在庫が推定されかねないし、ウクライナの在庫レベルが明らかになってしまう懸念もある。そのため、詳細は発表しなかったり、公表しているものの他に非公表の武器供与がおこなわれるケースもあるといわれる。
2024年4月に開かれたNATO外相会合では、ウクライナへの武器供与に関してNATOの直接的な役割を拡大する提案が議論された。ストルテンベルグ(Jens Stoltenberg)事務総長が、今後5年間で1,000億ドルにおよぶウクライナ支援パッケージとともに、ラムシュタイン会合を米国主導からNATO主導に変更する案を提示したようである。ウクライナにおける戦況が悪化し、ロシア軍が優位に立つと指摘されるなかで、ウクライナ支援を継続的に安定して実施するための提案である。特に念頭にあるのは、米国からの支援の停滞、そしてウクライナ支援に批判的なトランプ(Donald Trump)候補が大統領に当選した場合の影響への懸念である。
最終的にどのような形になるとしても、何かの継続的な実施を確保するためにNATOがより中心的な役割を果たすのは合理的である。NATOは2003年8月に、アフガニスタンでの治安支援活動(国際治安支援部隊:ISAF)の指揮権を引き継いだ。2001年末から、英国やドイツといった個別国が司令部を交代で担当していたのだが、一国で指揮を担える国が限定されることに加え、半年交代では効率が悪く、継続性を維持するためにNATOに白羽の矢が立ったのである。ISAFへの主要な兵力貢献国がNATO諸国だったことも背景に存在した。ラムシュタイン会合をNATO主導にする案は、ISAFの指揮権をNATOが引き継いだ論理に近い。
他方で、ウクライナへの経済支援や人道支援を含めた全体の支援額(表明額)ではEU(欧州連合)を含む欧州諸国が米国を上回るものの、武器供与に限定すれば米国の比重がいまだに欧州を上回っている。そのため、2023年末以降、米国議会を舞台にした内政上の対立によって米国のウクライナ支援がほぼ停止してしまったことが、戦況に直接的な影響をおよぼしているのである。欧州は米国の代替ができていない。これは意思の問題以前に能力の問題である。いくらウクライナ支援の意思があり米国の穴を埋めたくても、供与する武器が不足していては支援できないからである。欧州にとっては正念場だが、ラムシュタイン会合の主導権のみを米国からNATOに移したところで、支援の安定的な継続を確保できるとはいい切れないだろう。また、米国による支援の不確実性という構造的問題は、米国議会が当面のウクライナ支援予算を可決できたとしても変わらない。
ロシアが「勝利」したらどうするか
NATOとして新たな方策が必要だと認識されるようになった大きなきっかけは、戦場におけるロシア軍の優勢である。その結果、ロシアがこの戦争に「勝利」してしまうことへの懸念が増大した。「もしロシアが勝利すれば(if Russia wins)」という議論は、従来からさまざまな形でなされてきたものの、2024年に入って、それは、ウクライナ支援拡大を求めるレトリックとしてのみならず、実際の切迫した懸念になっている。
論者によってロシアの「勝利」としてイメージされるものは大きく異なるが、ロシア軍がウクライナ領内の占領地を拡大し、現在のウクライナ政府が崩壊したり、民主主義と独立を維持できなくなるような事態が概ね想定されている。NATOとしてこれを避けなければならない背景としては2つ指摘できる。
第1に、仮にウクライナが敗北してしまえば、「次なる標的はNATO諸国である」という危機感が存在する。「ウクライナで止まらないだろう」というのである。実際、北欧やポーランド、ドイツなどの首脳や閣僚から、今回の戦争後、遠くない将来にロシアがNATO諸国を侵略したり軍事的に威嚇したりする可能性が提起されている。この観点からすれば、欧州(NATO諸国)の自由と平和のために、いまはウクライナが代わりに戦ってくれている、ということになる。
第2に、ウクライナの自衛戦争に当初の想定以上に深入りしたがゆえに、この戦争の行方が持つNATOへの意味が拡大した。ウクライナの運命とNATOの運命の一体度が高まったのである。2022年2月の全面侵攻前と現在を比べると、ウクライナに対するNATO諸国の関与の度合いは大幅に上昇した。それは武器供与の急速な拡大や、ウクライナのNATO加盟が現実の問題として議論されるようになったことに象徴される。端的にいって、全面侵攻前や直後まで、ウクライナはNATOとロシアの間でいわば「宙ぶらりん」の状態にあった。今日でも、同国のNATO加盟が完全に既定路線になったとはいいにくいものの、それでも、「安全の保証」のあり方が真剣に議論され、ウクライナのNATO加盟が欧州全体の安全保障にとって必要であるとの議論も増えることになった。
こうした背景から、仮にロシアが「勝利」し、ウクライナが「敗北」するようなことになれば、欧州の安全保障全体、そしてNATOの信頼性が危機に瀕するとの認識が高まったのである。
それに実態面で追い討ちをかけるのが、ロシアにおける武器・弾薬生産の拡大である。今回のウクライナ全面侵攻によって、ロシアの特に陸上戦力は大きな損害を被ったものの、武器・弾薬生産が拡大したことによって、継戦能力が確保されたと同時に、ひとたび戦争が終了(ないし休止)すれば、数年で戦力を回復することができるとの試算が増えている。しかも、それは失敗と成功を含めて、実戦経験が豊富な軍隊である。これが欧州にとっての脅威にならないはずがない。ロシア軍に関するこうした評価は、NATO内でもさまざまに共有されているとみられる。
一部の欧州諸国の間では、こうした事態への対応がより具体的に議論されるようになっている。北欧やバルト諸国における徴兵制の強化や、ドイツのような徴兵制を廃止した国での復活議論はその代表的なものだが、ポーランドは、国防予算を対GDP(国内総生産)比で4%にする方向である。GDP比2%がNATO基準――ただし、従来は目標とされていたものの、現在では最低ラインとされている――の2倍の水準であり、ウクライナとロシア(飛地のカリニングラード)の両国と国境を接する同国の脅威認識が反映されている。
また、従来ロシアとの関係では煮え切らない姿勢を示してきたフランスが、ロシアに厳しい姿勢に本格的に舵を切ったようにみえるのも新しい展開である。2024年3月のテレビインタビューでマクロン(Emmanuel Macron)大統領は、「仮にウクライナが負ければ、フランスでの生活も大きく変わる。欧州の安全保障は失われる。プーチンがそこで止まると誰が信じられるだろうか」と警告したのである。
ただし、一部でそうした新たな危機感、切迫感が広がりつつあるものの、欧州全体として「戦時マインド」に移行したとはまだいえない。それは、(ポーランド以外の)国防予算の水準が緩やかにしか上昇していないことや、武器・弾薬の製造能力がなかなか拡大しないことからも窺われる。その意味で、欧州はまだ「平時マインド」で戦争に向き合っているのだといえる。
米国の信頼性低下にいかに対応するか
そうした状況をこれまで可能にしてきたのは、欧州の安全保障への米国のコミットメントであった。それは、有事の際には米国が助けてくれるという安心感であり、油断だった。完全なフリーライディング(ただ乗り)だとはいえないまでも、安全保障に関して、欧州が米国に依存し続け、それが長年の慣習になってきたことは否めない。
米国も欧州もそれを受け入れてきたから継続したのである。米国にとって、NATOを通じた欧州の安全保障へのコミットメントは確かにコストのかかるものではあったが、冷戦時代は、欧州(西欧)を失うことのコストは大きいものだったし、同時に、同盟国に対して強い指導力を発揮し、主導権をとることは米国の利益だとも認識されていた。対する欧州の側には、米国に主導され、振り回されることへのコストが存在していたが、ソ連に独力で対峙するコストに比べれば小さいものだった。その均衡点がNATOであり、それは「大西洋の取り引き(transatlantic bargain)」などと呼ばれた。
もっとも、同盟内のバードン・シェアリング(負担分担)は常に課題となり、米欧間、さらには欧州内で刺々しい議論がなされることも少なくなかった。ただし、それが同盟の抜本的な再編につながることはなかった。米国は、欧州の負担分担を増やしたいと考えつつ、主導権は維持したかったからである。パワーを維持したままで、バードンのみを分担させることはできない。少なくとも欧州の側がそれでは納得しない。
国防支出に関して米国の負担が過大であり、欧州に応分の負担を求めること自体には米国内でコンセンサスがある。欧州の国防支出拡大を求めたのはトランプ政権のみではない。言葉の使い方に違いはあったとしても、オバマ(Barack Obama)政権もブッシュ(George W. Bush)政権も同様だった。実際、対GDP比で2%の国防支出を NATOの目標として明示し、10年以内の達成努力に合意したのはオバマ時代の2014年だった。
それでも、トランプ政権に特徴があったとすれば、それは同盟の意味を軽視する姿勢だったといえる。トランプにとっての同盟はアセットではなく、コストに過ぎなかったのである。米国にとってのコスト計算という観点で、NATOのような同盟国とロシアや中国は同列に比較されることになった。
2024年11月の米国大統領選挙で、トランプ候補が再び当選することへの懸念が欧州で高まっている。4年は耐えられたものの、再びトランプ政権になってしまえば、次は耐えられないという懸念である。ウクライナにおけるロシアの「勝利」と米国におけるトランプ政権の誕生という2つの難題に同時に対処しなければならないのが欧州、そしてNATOの現実である。
後者に関しては、たとえトランプ候補が当選しなかったとしても決して問題が解決するわけではない点にも注意が必要だろう。というのも、対外関与を嫌う内向き姿勢はトランプ陣営のみの問題ではなく、米国の有権者の構造的傾向になっているからである。しかも、バイデン政権が継続したとしても、連邦議会が共和党多数になれば、政権の政策は大きな制約を受ける。実際、議会が必要な予算を承認しないことによって、2023年末からウクライナ支援はほぼ停止したのである。
トランプ政権が再び誕生した場合には、米国がNATOから離脱するかもしれないとも指摘される。その手続きについても注目が集まるものの、米国が他のNATO加盟国の防衛にコミットしたくないのであれば、必ずしもNATOから正式に離脱する必要はない。NATO加盟国の防衛のために部隊を送らないことを宣言したり、実際に有事の際に行動しなければよいだけだからである。抑止力を損ない、同盟を形骸化させるのは簡単なのである。
ただし、トランプとしても全ての同盟国を敵に回したくはないとすれば、NATOのなかから、一部の国を選んで関係を深める可能性も考えられる。実際、2017年から2021年までのトランプ政権期に、例えばポーランドとの関係は強化されたし、英国のジョンソン(Boris Johnson)首相との関係も良好だった。2024年の大統領選挙キャンペーンでは、「カネを払っていない国は助けない」と強調している。しかし、額面通りに受け取れば、「カネを払っている国は助ける」ということでもある。そして、トランプ政権時代には、GDP比で2%の国防支出を達成しているNATO加盟国を「2%組(2 percenters)」として優遇するような姿勢をみせた。
しかし、NATOにおける集団防衛が「カネ次第」で、しかもその基準が当初はGDP比2%だったとしても、3%などに容易に変化しかねないとすれば、やはり同盟の信頼性としては重大な問題になる。
ロシアの脅威と同様、米国の行方に関しても欧州は、最悪のシナリオを頭では考え、懸念を深めつつも、完全にマインドを変化させてコストのかかる自律路線に踏み出すのか否か、まだ様子見を続けている状況にある。そして、その背後には、「できればそのような道は歩みたくない」という本音が見え隠れする。これが、判断を遅らせてしまう致命的な失敗になるのか賢明な慎重さなのかはまだ分からない。75周年を迎えたNATOは正念場に立たされている。
執筆者プロフィール
鶴岡 路人(つるおか みちと)
慶應義塾大学総合政策学部 准教授
戦略構想センター(KCS)副センター長
慶應義塾大学法学部卒業後、同大学大学院、米ジョージタウン大学大学院を経て、英ロンドン大学キングス・カレッジで博士号取得。専門は国際安全保障、現代欧州政治。在ベルギー日本大使館専門調査員(NATO担当)を経て、2009年から2017年まで防衛省防衛研究所教官、主任研究官。その間、防衛省防衛政策局国際政策課部員、英王立防衛安全保障研究所(RUSI)訪問研究員を務める。2023年から2024年はオーストラリア国立大学訪問研究員。主著に『欧州戦争としてのウクライナ侵攻』(新潮選書、2023年)、『EU離脱――イギリスとヨーロッパの地殻変動』(ちくま新書、2020年)など。
慶應義塾大学総合政策学部 准教授
鶴岡 路人
1949年4月4日の北大西洋条約(ワシントン条約)署名から75年がたった。国家間の同盟が同じ基本条約のまま75周年を迎える事例はそれほど多くない。NATO(北大西洋条約機構)は、「史上最も成功した同盟」と呼ばれることも多い。
しかし、どれだけ成功していると考えるかは期待値次第でもある。全加盟国が一糸乱れぬ結束を常に維持していることが当然だという前提に立てば、現実のNATOはばらばらであり、低い評価をせざるをえない。他方、加盟各国の歴史や地理的条件が異なる以上、立場が一致しないのが当然だと考えれば、現実のNATOは期待以上という評価になるだろう。
NATOは、加盟国間の対立や同盟全体の危機の歴史としてみることも可能であれば、異なる立場を乗り越えてきた歴史だと捉えることもできる。どちらも真実である。そのうえでなお、今日のNATOは深刻な課題を抱えている。まさに苦悩する同盟だ。主なものは、継続的なウクライナ支援をいかに確保するのか、ロシアが「勝利」してしまった場合に欧州の安全保障をどのように維持するのか、そして米国の欧州への関与が本質的に弱まった場合にどう対応するのかの3つである。順にみていくことにしよう。
ウクライナ支援をいかに継続するか
2022年2月にはじまったロシアによるウクライナ全面侵攻に関して、NATOの最大の役割は加盟国の防衛であり、そのための対露抑止・防衛態勢の強化である。この点は重要で、同盟の観点では、ウクライナ支援が最重要課題なのではない。そして実際、バルト諸国やポーランドをはじめとして、ロシアやウクライナと国境を接するNATO加盟国の防衛強化のために、米国やその他諸国の部隊が派遣されている。
そのうえでNATOは、早期警戒管制機(AWACS)を主にポーランド上空などに飛ばし、そこからウクライナ領内を含めたロシアの航空機やミサイルを監視してきた。この情報の一部はウクライナにも提供されてきたといわれる。また、NATOの基金を通じて非殺傷兵器のウクライナへの供与が実施されてきた。加えて、50カ国以上にのぼるウクライナへの武器供与国の枠組みとして米国主導で開催されてきたウクライナ防衛コンタクトグループ(Ukraine Defense Contact Group:いわゆる「ラムシュタイン会合」)に関与し、ときに会合場所を提供してきたのがNATOである。
ただし、ウクライナへの殺傷武器の供与はウクライナとの二国間の合意に基づき各国が独自に実施してきた。ラムシュタイン会合では、ウクライナ側の要望を踏まえ、各国による供与内容の調整がおこなわれるが、最終的な判断を下すのは各国政府であるし、国によっては供与内容の詳細を発表しないこともある。その背後にはさまざまな事情が存在する。一部諸国ではロシアを刺激したくないという考慮がいまだに存在するし、また例えば供与する砲弾やミサイルの数を発表してしまっては、供与国側の残りの在庫が推定されかねないし、ウクライナの在庫レベルが明らかになってしまう懸念もある。そのため、詳細は発表しなかったり、公表しているものの他に非公表の武器供与がおこなわれるケースもあるといわれる。
2024年4月に開かれたNATO外相会合では、ウクライナへの武器供与に関してNATOの直接的な役割を拡大する提案が議論された。ストルテンベルグ(Jens Stoltenberg)事務総長が、今後5年間で1,000億ドルにおよぶウクライナ支援パッケージとともに、ラムシュタイン会合を米国主導からNATO主導に変更する案を提示したようである。ウクライナにおける戦況が悪化し、ロシア軍が優位に立つと指摘されるなかで、ウクライナ支援を継続的に安定して実施するための提案である。特に念頭にあるのは、米国からの支援の停滞、そしてウクライナ支援に批判的なトランプ(Donald Trump)候補が大統領に当選した場合の影響への懸念である。
最終的にどのような形になるとしても、何かの継続的な実施を確保するためにNATOがより中心的な役割を果たすのは合理的である。NATOは2003年8月に、アフガニスタンでの治安支援活動(国際治安支援部隊:ISAF)の指揮権を引き継いだ。2001年末から、英国やドイツといった個別国が司令部を交代で担当していたのだが、一国で指揮を担える国が限定されることに加え、半年交代では効率が悪く、継続性を維持するためにNATOに白羽の矢が立ったのである。ISAFへの主要な兵力貢献国がNATO諸国だったことも背景に存在した。ラムシュタイン会合をNATO主導にする案は、ISAFの指揮権をNATOが引き継いだ論理に近い。
他方で、ウクライナへの経済支援や人道支援を含めた全体の支援額(表明額)ではEU(欧州連合)を含む欧州諸国が米国を上回るものの、武器供与に限定すれば米国の比重がいまだに欧州を上回っている。そのため、2023年末以降、米国議会を舞台にした内政上の対立によって米国のウクライナ支援がほぼ停止してしまったことが、戦況に直接的な影響をおよぼしているのである。欧州は米国の代替ができていない。これは意思の問題以前に能力の問題である。いくらウクライナ支援の意思があり米国の穴を埋めたくても、供与する武器が不足していては支援できないからである。欧州にとっては正念場だが、ラムシュタイン会合の主導権のみを米国からNATOに移したところで、支援の安定的な継続を確保できるとはいい切れないだろう。また、米国による支援の不確実性という構造的問題は、米国議会が当面のウクライナ支援予算を可決できたとしても変わらない。
ロシアが「勝利」したらどうするか
NATOとして新たな方策が必要だと認識されるようになった大きなきっかけは、戦場におけるロシア軍の優勢である。その結果、ロシアがこの戦争に「勝利」してしまうことへの懸念が増大した。「もしロシアが勝利すれば(if Russia wins)」という議論は、従来からさまざまな形でなされてきたものの、2024年に入って、それは、ウクライナ支援拡大を求めるレトリックとしてのみならず、実際の切迫した懸念になっている。
論者によってロシアの「勝利」としてイメージされるものは大きく異なるが、ロシア軍がウクライナ領内の占領地を拡大し、現在のウクライナ政府が崩壊したり、民主主義と独立を維持できなくなるような事態が概ね想定されている。NATOとしてこれを避けなければならない背景としては2つ指摘できる。
第1に、仮にウクライナが敗北してしまえば、「次なる標的はNATO諸国である」という危機感が存在する。「ウクライナで止まらないだろう」というのである。実際、北欧やポーランド、ドイツなどの首脳や閣僚から、今回の戦争後、遠くない将来にロシアがNATO諸国を侵略したり軍事的に威嚇したりする可能性が提起されている。この観点からすれば、欧州(NATO諸国)の自由と平和のために、いまはウクライナが代わりに戦ってくれている、ということになる。
第2に、ウクライナの自衛戦争に当初の想定以上に深入りしたがゆえに、この戦争の行方が持つNATOへの意味が拡大した。ウクライナの運命とNATOの運命の一体度が高まったのである。2022年2月の全面侵攻前と現在を比べると、ウクライナに対するNATO諸国の関与の度合いは大幅に上昇した。それは武器供与の急速な拡大や、ウクライナのNATO加盟が現実の問題として議論されるようになったことに象徴される。端的にいって、全面侵攻前や直後まで、ウクライナはNATOとロシアの間でいわば「宙ぶらりん」の状態にあった。今日でも、同国のNATO加盟が完全に既定路線になったとはいいにくいものの、それでも、「安全の保証」のあり方が真剣に議論され、ウクライナのNATO加盟が欧州全体の安全保障にとって必要であるとの議論も増えることになった。
こうした背景から、仮にロシアが「勝利」し、ウクライナが「敗北」するようなことになれば、欧州の安全保障全体、そしてNATOの信頼性が危機に瀕するとの認識が高まったのである。
それに実態面で追い討ちをかけるのが、ロシアにおける武器・弾薬生産の拡大である。今回のウクライナ全面侵攻によって、ロシアの特に陸上戦力は大きな損害を被ったものの、武器・弾薬生産が拡大したことによって、継戦能力が確保されたと同時に、ひとたび戦争が終了(ないし休止)すれば、数年で戦力を回復することができるとの試算が増えている。しかも、それは失敗と成功を含めて、実戦経験が豊富な軍隊である。これが欧州にとっての脅威にならないはずがない。ロシア軍に関するこうした評価は、NATO内でもさまざまに共有されているとみられる。
一部の欧州諸国の間では、こうした事態への対応がより具体的に議論されるようになっている。北欧やバルト諸国における徴兵制の強化や、ドイツのような徴兵制を廃止した国での復活議論はその代表的なものだが、ポーランドは、国防予算を対GDP(国内総生産)比で4%にする方向である。GDP比2%がNATO基準――ただし、従来は目標とされていたものの、現在では最低ラインとされている――の2倍の水準であり、ウクライナとロシア(飛地のカリニングラード)の両国と国境を接する同国の脅威認識が反映されている。
また、従来ロシアとの関係では煮え切らない姿勢を示してきたフランスが、ロシアに厳しい姿勢に本格的に舵を切ったようにみえるのも新しい展開である。2024年3月のテレビインタビューでマクロン(Emmanuel Macron)大統領は、「仮にウクライナが負ければ、フランスでの生活も大きく変わる。欧州の安全保障は失われる。プーチンがそこで止まると誰が信じられるだろうか」と警告したのである。
ただし、一部でそうした新たな危機感、切迫感が広がりつつあるものの、欧州全体として「戦時マインド」に移行したとはまだいえない。それは、(ポーランド以外の)国防予算の水準が緩やかにしか上昇していないことや、武器・弾薬の製造能力がなかなか拡大しないことからも窺われる。その意味で、欧州はまだ「平時マインド」で戦争に向き合っているのだといえる。
米国の信頼性低下にいかに対応するか
そうした状況をこれまで可能にしてきたのは、欧州の安全保障への米国のコミットメントであった。それは、有事の際には米国が助けてくれるという安心感であり、油断だった。完全なフリーライディング(ただ乗り)だとはいえないまでも、安全保障に関して、欧州が米国に依存し続け、それが長年の慣習になってきたことは否めない。
米国も欧州もそれを受け入れてきたから継続したのである。米国にとって、NATOを通じた欧州の安全保障へのコミットメントは確かにコストのかかるものではあったが、冷戦時代は、欧州(西欧)を失うことのコストは大きいものだったし、同時に、同盟国に対して強い指導力を発揮し、主導権をとることは米国の利益だとも認識されていた。対する欧州の側には、米国に主導され、振り回されることへのコストが存在していたが、ソ連に独力で対峙するコストに比べれば小さいものだった。その均衡点がNATOであり、それは「大西洋の取り引き(transatlantic bargain)」などと呼ばれた。
もっとも、同盟内のバードン・シェアリング(負担分担)は常に課題となり、米欧間、さらには欧州内で刺々しい議論がなされることも少なくなかった。ただし、それが同盟の抜本的な再編につながることはなかった。米国は、欧州の負担分担を増やしたいと考えつつ、主導権は維持したかったからである。パワーを維持したままで、バードンのみを分担させることはできない。少なくとも欧州の側がそれでは納得しない。
国防支出に関して米国の負担が過大であり、欧州に応分の負担を求めること自体には米国内でコンセンサスがある。欧州の国防支出拡大を求めたのはトランプ政権のみではない。言葉の使い方に違いはあったとしても、オバマ(Barack Obama)政権もブッシュ(George W. Bush)政権も同様だった。実際、対GDP比で2%の国防支出を NATOの目標として明示し、10年以内の達成努力に合意したのはオバマ時代の2014年だった。
それでも、トランプ政権に特徴があったとすれば、それは同盟の意味を軽視する姿勢だったといえる。トランプにとっての同盟はアセットではなく、コストに過ぎなかったのである。米国にとってのコスト計算という観点で、NATOのような同盟国とロシアや中国は同列に比較されることになった。
2024年11月の米国大統領選挙で、トランプ候補が再び当選することへの懸念が欧州で高まっている。4年は耐えられたものの、再びトランプ政権になってしまえば、次は耐えられないという懸念である。ウクライナにおけるロシアの「勝利」と米国におけるトランプ政権の誕生という2つの難題に同時に対処しなければならないのが欧州、そしてNATOの現実である。
後者に関しては、たとえトランプ候補が当選しなかったとしても決して問題が解決するわけではない点にも注意が必要だろう。というのも、対外関与を嫌う内向き姿勢はトランプ陣営のみの問題ではなく、米国の有権者の構造的傾向になっているからである。しかも、バイデン政権が継続したとしても、連邦議会が共和党多数になれば、政権の政策は大きな制約を受ける。実際、議会が必要な予算を承認しないことによって、2023年末からウクライナ支援はほぼ停止したのである。
トランプ政権が再び誕生した場合には、米国がNATOから離脱するかもしれないとも指摘される。その手続きについても注目が集まるものの、米国が他のNATO加盟国の防衛にコミットしたくないのであれば、必ずしもNATOから正式に離脱する必要はない。NATO加盟国の防衛のために部隊を送らないことを宣言したり、実際に有事の際に行動しなければよいだけだからである。抑止力を損ない、同盟を形骸化させるのは簡単なのである。
ただし、トランプとしても全ての同盟国を敵に回したくはないとすれば、NATOのなかから、一部の国を選んで関係を深める可能性も考えられる。実際、2017年から2021年までのトランプ政権期に、例えばポーランドとの関係は強化されたし、英国のジョンソン(Boris Johnson)首相との関係も良好だった。2024年の大統領選挙キャンペーンでは、「カネを払っていない国は助けない」と強調している。しかし、額面通りに受け取れば、「カネを払っている国は助ける」ということでもある。そして、トランプ政権時代には、GDP比で2%の国防支出を達成しているNATO加盟国を「2%組(2 percenters)」として優遇するような姿勢をみせた。
しかし、NATOにおける集団防衛が「カネ次第」で、しかもその基準が当初はGDP比2%だったとしても、3%などに容易に変化しかねないとすれば、やはり同盟の信頼性としては重大な問題になる。
ロシアの脅威と同様、米国の行方に関しても欧州は、最悪のシナリオを頭では考え、懸念を深めつつも、完全にマインドを変化させてコストのかかる自律路線に踏み出すのか否か、まだ様子見を続けている状況にある。そして、その背後には、「できればそのような道は歩みたくない」という本音が見え隠れする。これが、判断を遅らせてしまう致命的な失敗になるのか賢明な慎重さなのかはまだ分からない。75周年を迎えたNATOは正念場に立たされている。
執筆者プロフィール
鶴岡 路人(つるおか みちと)
慶應義塾大学総合政策学部 准教授
戦略構想センター(KCS)副センター長
慶應義塾大学法学部卒業後、同大学大学院、米ジョージタウン大学大学院を経て、英ロンドン大学キングス・カレッジで博士号取得。専門は国際安全保障、現代欧州政治。在ベルギー日本大使館専門調査員(NATO担当)を経て、2009年から2017年まで防衛省防衛研究所教官、主任研究官。その間、防衛省防衛政策局国際政策課部員、英王立防衛安全保障研究所(RUSI)訪問研究員を務める。2023年から2024年はオーストラリア国立大学訪問研究員。主著に『欧州戦争としてのウクライナ侵攻』(新潮選書、2023年)、『EU離脱――イギリスとヨーロッパの地殻変動』(ちくま新書、2020年)など。

