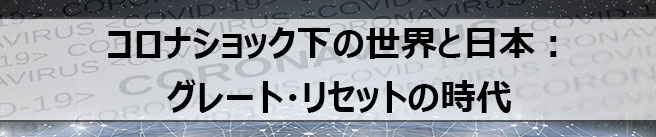
(16) 中国と中・東欧諸国の関係の発展と減速
――日本の「見落とし」の背景にあるもの
――日本の「見落とし」の背景にあるもの

掲載日:2021年8月20日
筑波大学人文社会系准教授
東野 篤子
はじめに
中国の一帯一路がもたらしたグローバルな影響を考察する際、中・東欧諸国の経験は非常に興味深い事例を提示してきた。一帯一路が正式に発表されたのは2013年9月のことであったが、それに先立つ2012年4月に、中・東欧諸国と中国は「16+1」という協力枠組みを発足させ、協力を制度化させていた (※1) 。本稿ではまず、この「16+1」の枠組みを用いて中国との経済関係強化を期待した中・東欧諸国が、なぜ近年顕著な「中国離れ」を起こしているのかを、時系列的に論じていく。
このうえで本稿が問題視するのは、日本がこの「16+1」を初めとした中国と中・東欧との関係構築にほとんど関心を払ってこなかったという点である。中・東欧と中国との関係は、ある特定の地域における一帯一路の過熱と失速を観察する上で極めて重要な事例であったにもかかわらず、日本でこの現象が真剣に分析されたことは、ごく最近まで非常に少なかったと云ってよい。本稿ではその背景として、日本における国際関係への視角――米中対立やヨーロッパ全体の情勢、中・東欧諸国の状況に対する日本の見方――にどのような特色があり、日本が中・東欧に向ける眼差しにどのように影響してきたのかについて考察した上で、今後中・東欧諸国と日本との協力関係の構築に向けた課題について考察したい。
一帯一路の試金石としての中・東欧
中国にとって中・東欧諸国は、EU市場への重要なゲートウエイであり、ヨーロッパにおける一帯一路の試金石と位置づけられていた。2000年代後半以降に相次いだ経済危機で大きなダメージを受けていたにもかかわらず、EUから十分な支援や投資を受けることが出来なかった中・東欧諸国は、中国の参入を大いに歓迎した。
中国による中・東欧諸国への投資案件の多くが高額かつ大規模なインフラ事業であったことも、中・東欧諸国にとっては大きな魅力の一つだった。さらに中・東欧諸国にとっては、「16+1」を通じて習近平国家主席や李克強首相、王毅外相らと定期的な協議の実施が可能となったのも、大きなメリットと考えられていた。
中国と中・東欧との急接近は、一帯一路の成功例として次第に国際的な注目を集めるようになった。それと並行して、EUや米国は2010年代半ば以降、中・東欧における中国の動きを警戒するようになった。
「16+1」には、2004年以降にEU加盟を果たしたポーランドやハンガリー等の10カ国と、EUへの加盟を目指すセルビアやモンテネグロなどの西バルカンの6カ国が含まれる。中国は、EU加盟国と非加盟国が混在する枠組みをあえて形成し、EUの直接的なコントロールを及びにくくすることを意図していたのではないかとの指摘さえあった (※2) 。現に、中国が当該地域に投資等を行う際には、EUの投資ルールや規則、手続きからの逸脱がしばしば見られ、EUはその対策に苦慮していた。
EUはこれを、中国によるヨーロッパの「分断統治(divide and rule)」と見なし、不透明で実現可能性にも問題がある投資案件を次々に中・東欧に持ちかける中国を牽制する一方、そうした案件を歓迎した中・東欧諸国にも、疑念の眼差しを注いできたのである (※3) 。
中国の影響力の終焉?
結局「16+1」を通じた中国の対中・東欧投資は、多額のコミットがなされたものの、その多くが実現されず、実現されても大幅に遅れたり、当初の想定を遙かに超える莫大な費用がかかることが明らかとなったりしてきた。インフラ工事のための労働力も全て中国から調達したため、中・東欧現地の雇用も促進されなかった。「16+1」の枠組みを用いて中国と協議を行い、中国の市場開放を促すことを試みていたバルト諸国なども、頑なに市場開放に応じない中国の態度に失望を隠さなくなった。このため、中国からの投資に対する中・東欧の期待は大きく損なわれていった。米トランプ政権が中・東欧諸国に対して、HUAWEI製品の不使用等を含め、対中アプローチの見直しを粘り強く働きかけたことも奏功し、複数の中・東欧諸国はHUAWEI製品排除を表明している。
「16+1」の大きなメリットと思われてきた中国執行部との協議も、中国からの大型投資が期待できない以上、もはや魅力ではなくなったと見られる。2021年2月にオンライン実施された「16+1」の首脳会議には、習近平自らが出席したにもかかわらず、「16+1」側からは6カ国もの参加国が首脳の出席を見合わせたことが、これを雄弁に物語っていた (※4) 。2021年5月にはリトアニアが、「『16+1』からは得られるものがなにもなかった」として、「16+1」からの離脱を表明した。
これらを総合的に勘案すると、中・東欧で中国が政治・経済の両面において強い影響力を誇った時代は、徐々に終わりを告げようとしているとみるのが妥当であろう。
日本にとっての「16+1」――なぜ関心をもたれなかったのか
ところで、日本においても一帯一路に対する関心(および警戒感)は全般に強く、様々な分析が行われてきた。しかし、その分析対象は東南アジア等が圧倒的に多く、「16+1」をはじめとした中・東欧と中国との関係強化の動きは日本にはほとんど伝えられてこなかったといえる。すでに述べたように「16+1」は、ある地域における中国の影響力が急激に強まり、その後徐々に希薄化していくまでの極めて興味深いプロセスを示している。その意味では「16+1」は、ヨーロッパに対する観察としてだけではなく、中国に対する観察としても、重要な事例であったはずである。しかし日本の関心が「16+1」にようやく向けられるようになったのは、「16+1」の影響力の失墜が広く意識され始めた2020年以降であったとみて良いだろう。
一帯一路の事例としての中・東欧が日本で注目されなかったことには複合的な理由が存在するのであろうが、ここでとくに指摘しておくべきは、日本にとっての対外的な関心事項の大部分が米国と中国の二大国とその対立に占められていただけでなく、それを含めたあらゆる国際的な現象を日本に直接関係する部分でしか理解しようとしない傾向が存在していたということではないだろうか (※5) 。本来、中・東欧における中国の影響力増大は、日本にとっての最大の関心事である中国の動きを見る上でも欠かせないはずだった。しかし、中国の動きや米中関係を、純粋に日本と関連する部分だけで見ようとするあまりに、日本との経済関係が他地域と比較して強固とはいえないような中・東欧諸国での諸現象を見落しがちであったのではないか。
日本の関心が全くヨーロッパ・中国関係に向かなかったわけではない。しかし、その場合にも、英国やドイツなどの「大国」がもっぱら注目を集めていたことは否定しがたい。2015年の英国のキャメロン首相による「英中関係の黄金時代」発言や (※6) 、英国を初めとした欧州諸国が中国主導のアジアインフラ投資銀行(AIIB)に参加を表明したこと、イタリアが一帯一路の覚書に署名したこと、メルケルが在任期間の15年間に12回中国を訪問したこと(日本訪問は5回)等は、日本でも大きく取り上げられた (※7) 。
現状では、ヨーロッパ・中国関係はその「蜜月時代」から大きく変化しており、中国との関係を極めて重視すると公言してはばからない国は、ハンガリーやセルビアなど、ごく僅かである (※8) 。英国はとりわけジョンソン政権成立後、人権問題等を理由に対中強硬姿勢に大きく舵を切った。イタリアは一帯一路で大きな成果を出すことがなかったことから、覚書署名を推進した政権与党に対する批判が高まっている。ドイツも中国との緊密な経済関係と人権問題との間で揺れつつ、ポストメルケル時代の対中戦略形成に向けて試行錯誤している。しかし日本では、既述のような2010年代半ばの状況のヨーロッパ大国の印象が強烈だったせいか、そういったヨーロッパにおける方向転換や試行錯誤には十分な関心を向けることなく、「ヨーロッパは中国に甘い」というイメージを抱き続けているともいえる (※9) 。中・東欧諸国はそのような文脈の中で、ドイツと「同様」に、「経済偏重」の対中関係を有してきたと、日本では見られ続けている (※10) 。すでに述べたとおり、実際には中・東欧の対中期待は大きく下がっているものの、こうした現象に日本からのきめ細かな観察が及ぶことは非常に稀であった。
ポスト一帯一路を見据えた日本と中・東欧諸国――新たな協働の可能性に向けて
最後に、逆説的ではあるが、冷戦直後期の日本の対中・東欧政策が一定のダイナミックさを有しており、日本としてもその自覚があったからこそ、近年の「16+1」等の中・東欧情勢に無頓着になりがちであったという側面があったことも指摘しておかなければならないだろう。たしかに、1989年の「東欧革命」直後に海部政権が実施した中・東欧支援は広範かつ大規模であり (※11) 、高く評価するに値するものであった。またハンガリーにおけるマジャール・スズキの成功例にも見られるとおり、日本の民間企業の中・東欧進出が顕著であった時期もあった。2003年から2004年にかけての時期において、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーの、いわゆる「V4」諸国との間で「V4+日本」対話・協力が開始され、外相会合や高級事務レベル政策対話が開催されてきたことも、重要な外交的成果であった。
しかしそうではあっても、その後の日本による中・東欧との関係構築努力は十分であったとは言いがたい。日本からの対中・東欧投資も、まずは韓国に、次に中国に凌駕されるようになった。また中・東欧諸国からの継続的な求めにもかかわらず、日本の首相、外務大臣の中・東欧訪問はつい最近まで非常に稀であった (※12) 。すなわち、中・東欧諸国が日本に対して有する期待と、日本が中・東欧諸国に対して実際に行うコミットメントとの間に、差が生じるようになってきたのである。中国の対中・東欧進出は、日本の対中・東欧アプローチが積極的とは言えなかった時期にも合致するのだが、「16+1」を軸とした中国と中・東欧の急接近に日本が危機感を持つようになったのは、つい最近のことなのである。
この文脈からすれば、2021年以降、茂木外相が中・東欧を重点的に訪問(5月にスロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド。7月にエストニア、ラトビア、リトアニア)していることは、日本とこれら諸国との関係のてこ入れに向けて望ましいことではある。ただし、こうした外交努力も日本の文脈ではしばしば、「対中牽制」の観点に偏って語られがちである。 (※13) しかし、日本が中・東欧諸国に対して、一帯一路や対中接近の問題点を今更説こうとするのであれば、それは「周回遅れ」と言わざるを得ない。本稿で繰り返し指摘してきたように、中・東欧諸国は中国との関係において、すでに期待と失望の双方を体験している。日本が直接に接したことのない中国の顔を、これら諸国は知っているとさえいえるだろう。
また、日本が中・東欧諸国を対中牽制の「手段」としてみている限りにおいては、中・東欧諸国からの真の信頼を日本が勝ち得ることはないであろう。仮に日本が中・東欧諸国を中国から「引き離す」ことに成功したとして、その後に日本と中・東欧諸国とで共に何をなそうとするのか。その具体性と実現可能性こそが問われているのである。
現在、国際的に強い関心を集めているのが、一帯一路に替わるインフラと支援の構想策定である。2021年7月のG7サミットで示された「より良い世界の再建(B3W)」等はその一例である。中・東欧諸国自身も、2016年に「三海洋イニシャティブ(Three Seas Initiative)」と呼ばれる地域的枠組みを発足させ、EUや米国等の協力を得ながら、独自のインフラ構築に向けた協力に取り組んでいる。日本は中・東欧諸国への関心を中国からの「引き離し」にのみ限定させるのではなく、これらの国々の真のニーズを十分に理解した上で、ポスト一帯一路の秩序をこれらの国々と共に検討し、構築していく必要がある。その努力こそが、中・東欧諸国と日本の関係を真に多層的なものへと変化させるうえで不可欠といえるであろう。
※1 「16+1」EUに加盟している11カ国(ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、ポーランド、クロアチア、スロベニア、スロバキア、チェコ、リトアニア、ラトビア、エストニア)、そしてEUに未加盟の加盟候補国および潜在的加盟候補国の5カ国(ボスニア=ヘルツェゴビナ、セルビア、北マケドニア、モンテネグロ、アルバニア)の、合計16カ国で2012年に発足した。2019年にギリシャが参加し、参加国が17になったことに伴い、「17+1」と改称された(なお中国側はこれを、「中国-中東欧首脳会議(China-CEEC Summit)」と称している)。しかし本論でも述べるとおり、2021年5月にはリトアニアが「17+1」からの離脱を表明したため、現状の参加国はまた16カ国に戻っている。本論では混乱を避けるため、本来であれば「17+1」と標記すべき2019年4月から2021年5月までの時期に関しても、「16+1」で統一することとする。
※2 Martin Hala, “Europe’s new ‘Eastern Bloc’,” Politico.eu, April 13, 2018; Jame Kynge and Michael Peel, “Brussels rattled as China reaches out to eastern Europe,” Financial Times, November 27, 2017.
※3 東野 篤子「ヨーロッパと一帯一路――脅威認識・落胆・期待の共存」『国際安全保障』47巻1号、2019年。
※4 東野 篤子『中東欧・中国関係の変質と 「17+1」首脳会合』ROLES REPORT No.1 https://roles.rcast.u-tokyo.ac.jp/publication/1
※5 ただし、佐橋亮『米中対立――アメリカの戦略転換と分断される世界』(中公新書、2021年)では、米中対立におけるヨーロッパの立ち位置にも丁寧に触れられている。
※6 Foreign and Commonwealth Office, UK-China Joint Statement on Building a Global Comprehensive Strategic Partnership for the 21st Century, October 22, 2015.
※7 「嫌米と中国依存に揺れるメルケル独首相の花道」『日本経済新聞』2020年8月28日 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63057170W0A820C2000000/
※8 そのハンガリーにおいてでさえ、中国からの多額の借り入れを行ってブダペストに復旦大学を開校するという政府案に対し、国内からの反発が強くなっていることには留意すべきであろう。Panyi, Szabolcs “The Fight Over Fudan: A Chinese University in Budapest Sparks Reckoning for Sino-Hungarian Relations,” 7 June 2021. https://chinaobservers.eu/the-fight-over-fudan-a-chinese-university-in-budapest-sparks-reckoning-for-sino-hungarian-relations/
※9 この指摘については以下を参照。鶴岡路人「イントロダクション 戦略的自律を目指す欧州 試される日本の外交力」『Wedge Report』 2021年1月18日、 January. https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21836
※10 そういった問題意識を反映した日本における報道の一例として、「[社説]日欧連携を地域安定に生かせ」『日本経済新聞』2021年5月28日。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK285140Y1A520C2000000/
※11 東欧革命直後の時期における、日本による対中・東欧諸国支援については、例えば以下の海部俊樹内閣総理大臣の演説(1990年1月9日)を参照。 https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/exdpm/19900109.S1J.html
※12 たとえば、中・東欧地域の中心的存在であるいわゆる「ヴィシェグラード4カ国(V4)」に対してですら、日本の政治家の訪問は限定的であった。2013年6月の安倍首相(当時)のポーランド訪問は、日本の首相としては10年ぶりであった。また、2019年4月の安倍首相(同)のスロバキア訪問は、日本の首相として初めてであった。ハンガリーには1990年に海部俊樹総理が、チェコには2003年に小泉純一郎総理が訪問したのが、それぞれ最後である。
※13 「東欧4カ国と自由な国際秩序で一致 中国にらみ外相会談」『日本経済新聞』2021年5月7日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA077010X00C21A5000000/; 「日本の対中懸念に『強い共感』外相、バルト3国を歴訪」『朝日新聞』2021年7月3日 https://digital.asahi.com/articles/ASP7376NXP73UTFK00D.html
執筆者プロフィール
東野篤子(ひがしの・あつこ)
筑波大学人文社会系准教授
慶應義塾大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院修士課程修了、英国バーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程修了(Ph.D)。広島市立大学准教授などを経て、筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授、専門はヨーロッパ国際政治、国際関係論。共著に『変わりゆくEU
――永遠平和のプロジェクトの行方』明石書店、2020年等。
筑波大学人文社会系准教授
東野 篤子
はじめに
中国の一帯一路がもたらしたグローバルな影響を考察する際、中・東欧諸国の経験は非常に興味深い事例を提示してきた。一帯一路が正式に発表されたのは2013年9月のことであったが、それに先立つ2012年4月に、中・東欧諸国と中国は「16+1」という協力枠組みを発足させ、協力を制度化させていた (※1) 。本稿ではまず、この「16+1」の枠組みを用いて中国との経済関係強化を期待した中・東欧諸国が、なぜ近年顕著な「中国離れ」を起こしているのかを、時系列的に論じていく。
このうえで本稿が問題視するのは、日本がこの「16+1」を初めとした中国と中・東欧との関係構築にほとんど関心を払ってこなかったという点である。中・東欧と中国との関係は、ある特定の地域における一帯一路の過熱と失速を観察する上で極めて重要な事例であったにもかかわらず、日本でこの現象が真剣に分析されたことは、ごく最近まで非常に少なかったと云ってよい。本稿ではその背景として、日本における国際関係への視角――米中対立やヨーロッパ全体の情勢、中・東欧諸国の状況に対する日本の見方――にどのような特色があり、日本が中・東欧に向ける眼差しにどのように影響してきたのかについて考察した上で、今後中・東欧諸国と日本との協力関係の構築に向けた課題について考察したい。
一帯一路の試金石としての中・東欧
中国にとって中・東欧諸国は、EU市場への重要なゲートウエイであり、ヨーロッパにおける一帯一路の試金石と位置づけられていた。2000年代後半以降に相次いだ経済危機で大きなダメージを受けていたにもかかわらず、EUから十分な支援や投資を受けることが出来なかった中・東欧諸国は、中国の参入を大いに歓迎した。
中国による中・東欧諸国への投資案件の多くが高額かつ大規模なインフラ事業であったことも、中・東欧諸国にとっては大きな魅力の一つだった。さらに中・東欧諸国にとっては、「16+1」を通じて習近平国家主席や李克強首相、王毅外相らと定期的な協議の実施が可能となったのも、大きなメリットと考えられていた。
中国と中・東欧との急接近は、一帯一路の成功例として次第に国際的な注目を集めるようになった。それと並行して、EUや米国は2010年代半ば以降、中・東欧における中国の動きを警戒するようになった。
「16+1」には、2004年以降にEU加盟を果たしたポーランドやハンガリー等の10カ国と、EUへの加盟を目指すセルビアやモンテネグロなどの西バルカンの6カ国が含まれる。中国は、EU加盟国と非加盟国が混在する枠組みをあえて形成し、EUの直接的なコントロールを及びにくくすることを意図していたのではないかとの指摘さえあった (※2) 。現に、中国が当該地域に投資等を行う際には、EUの投資ルールや規則、手続きからの逸脱がしばしば見られ、EUはその対策に苦慮していた。
EUはこれを、中国によるヨーロッパの「分断統治(divide and rule)」と見なし、不透明で実現可能性にも問題がある投資案件を次々に中・東欧に持ちかける中国を牽制する一方、そうした案件を歓迎した中・東欧諸国にも、疑念の眼差しを注いできたのである (※3) 。
中国の影響力の終焉?
結局「16+1」を通じた中国の対中・東欧投資は、多額のコミットがなされたものの、その多くが実現されず、実現されても大幅に遅れたり、当初の想定を遙かに超える莫大な費用がかかることが明らかとなったりしてきた。インフラ工事のための労働力も全て中国から調達したため、中・東欧現地の雇用も促進されなかった。「16+1」の枠組みを用いて中国と協議を行い、中国の市場開放を促すことを試みていたバルト諸国なども、頑なに市場開放に応じない中国の態度に失望を隠さなくなった。このため、中国からの投資に対する中・東欧の期待は大きく損なわれていった。米トランプ政権が中・東欧諸国に対して、HUAWEI製品の不使用等を含め、対中アプローチの見直しを粘り強く働きかけたことも奏功し、複数の中・東欧諸国はHUAWEI製品排除を表明している。
「16+1」の大きなメリットと思われてきた中国執行部との協議も、中国からの大型投資が期待できない以上、もはや魅力ではなくなったと見られる。2021年2月にオンライン実施された「16+1」の首脳会議には、習近平自らが出席したにもかかわらず、「16+1」側からは6カ国もの参加国が首脳の出席を見合わせたことが、これを雄弁に物語っていた (※4) 。2021年5月にはリトアニアが、「『16+1』からは得られるものがなにもなかった」として、「16+1」からの離脱を表明した。
これらを総合的に勘案すると、中・東欧で中国が政治・経済の両面において強い影響力を誇った時代は、徐々に終わりを告げようとしているとみるのが妥当であろう。
日本にとっての「16+1」――なぜ関心をもたれなかったのか
ところで、日本においても一帯一路に対する関心(および警戒感)は全般に強く、様々な分析が行われてきた。しかし、その分析対象は東南アジア等が圧倒的に多く、「16+1」をはじめとした中・東欧と中国との関係強化の動きは日本にはほとんど伝えられてこなかったといえる。すでに述べたように「16+1」は、ある地域における中国の影響力が急激に強まり、その後徐々に希薄化していくまでの極めて興味深いプロセスを示している。その意味では「16+1」は、ヨーロッパに対する観察としてだけではなく、中国に対する観察としても、重要な事例であったはずである。しかし日本の関心が「16+1」にようやく向けられるようになったのは、「16+1」の影響力の失墜が広く意識され始めた2020年以降であったとみて良いだろう。
一帯一路の事例としての中・東欧が日本で注目されなかったことには複合的な理由が存在するのであろうが、ここでとくに指摘しておくべきは、日本にとっての対外的な関心事項の大部分が米国と中国の二大国とその対立に占められていただけでなく、それを含めたあらゆる国際的な現象を日本に直接関係する部分でしか理解しようとしない傾向が存在していたということではないだろうか (※5) 。本来、中・東欧における中国の影響力増大は、日本にとっての最大の関心事である中国の動きを見る上でも欠かせないはずだった。しかし、中国の動きや米中関係を、純粋に日本と関連する部分だけで見ようとするあまりに、日本との経済関係が他地域と比較して強固とはいえないような中・東欧諸国での諸現象を見落しがちであったのではないか。
日本の関心が全くヨーロッパ・中国関係に向かなかったわけではない。しかし、その場合にも、英国やドイツなどの「大国」がもっぱら注目を集めていたことは否定しがたい。2015年の英国のキャメロン首相による「英中関係の黄金時代」発言や (※6) 、英国を初めとした欧州諸国が中国主導のアジアインフラ投資銀行(AIIB)に参加を表明したこと、イタリアが一帯一路の覚書に署名したこと、メルケルが在任期間の15年間に12回中国を訪問したこと(日本訪問は5回)等は、日本でも大きく取り上げられた (※7) 。
現状では、ヨーロッパ・中国関係はその「蜜月時代」から大きく変化しており、中国との関係を極めて重視すると公言してはばからない国は、ハンガリーやセルビアなど、ごく僅かである (※8) 。英国はとりわけジョンソン政権成立後、人権問題等を理由に対中強硬姿勢に大きく舵を切った。イタリアは一帯一路で大きな成果を出すことがなかったことから、覚書署名を推進した政権与党に対する批判が高まっている。ドイツも中国との緊密な経済関係と人権問題との間で揺れつつ、ポストメルケル時代の対中戦略形成に向けて試行錯誤している。しかし日本では、既述のような2010年代半ばの状況のヨーロッパ大国の印象が強烈だったせいか、そういったヨーロッパにおける方向転換や試行錯誤には十分な関心を向けることなく、「ヨーロッパは中国に甘い」というイメージを抱き続けているともいえる (※9) 。中・東欧諸国はそのような文脈の中で、ドイツと「同様」に、「経済偏重」の対中関係を有してきたと、日本では見られ続けている (※10) 。すでに述べたとおり、実際には中・東欧の対中期待は大きく下がっているものの、こうした現象に日本からのきめ細かな観察が及ぶことは非常に稀であった。
ポスト一帯一路を見据えた日本と中・東欧諸国――新たな協働の可能性に向けて
最後に、逆説的ではあるが、冷戦直後期の日本の対中・東欧政策が一定のダイナミックさを有しており、日本としてもその自覚があったからこそ、近年の「16+1」等の中・東欧情勢に無頓着になりがちであったという側面があったことも指摘しておかなければならないだろう。たしかに、1989年の「東欧革命」直後に海部政権が実施した中・東欧支援は広範かつ大規模であり (※11) 、高く評価するに値するものであった。またハンガリーにおけるマジャール・スズキの成功例にも見られるとおり、日本の民間企業の中・東欧進出が顕著であった時期もあった。2003年から2004年にかけての時期において、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーの、いわゆる「V4」諸国との間で「V4+日本」対話・協力が開始され、外相会合や高級事務レベル政策対話が開催されてきたことも、重要な外交的成果であった。
しかしそうではあっても、その後の日本による中・東欧との関係構築努力は十分であったとは言いがたい。日本からの対中・東欧投資も、まずは韓国に、次に中国に凌駕されるようになった。また中・東欧諸国からの継続的な求めにもかかわらず、日本の首相、外務大臣の中・東欧訪問はつい最近まで非常に稀であった (※12) 。すなわち、中・東欧諸国が日本に対して有する期待と、日本が中・東欧諸国に対して実際に行うコミットメントとの間に、差が生じるようになってきたのである。中国の対中・東欧進出は、日本の対中・東欧アプローチが積極的とは言えなかった時期にも合致するのだが、「16+1」を軸とした中国と中・東欧の急接近に日本が危機感を持つようになったのは、つい最近のことなのである。
この文脈からすれば、2021年以降、茂木外相が中・東欧を重点的に訪問(5月にスロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド。7月にエストニア、ラトビア、リトアニア)していることは、日本とこれら諸国との関係のてこ入れに向けて望ましいことではある。ただし、こうした外交努力も日本の文脈ではしばしば、「対中牽制」の観点に偏って語られがちである。 (※13) しかし、日本が中・東欧諸国に対して、一帯一路や対中接近の問題点を今更説こうとするのであれば、それは「周回遅れ」と言わざるを得ない。本稿で繰り返し指摘してきたように、中・東欧諸国は中国との関係において、すでに期待と失望の双方を体験している。日本が直接に接したことのない中国の顔を、これら諸国は知っているとさえいえるだろう。
また、日本が中・東欧諸国を対中牽制の「手段」としてみている限りにおいては、中・東欧諸国からの真の信頼を日本が勝ち得ることはないであろう。仮に日本が中・東欧諸国を中国から「引き離す」ことに成功したとして、その後に日本と中・東欧諸国とで共に何をなそうとするのか。その具体性と実現可能性こそが問われているのである。
現在、国際的に強い関心を集めているのが、一帯一路に替わるインフラと支援の構想策定である。2021年7月のG7サミットで示された「より良い世界の再建(B3W)」等はその一例である。中・東欧諸国自身も、2016年に「三海洋イニシャティブ(Three Seas Initiative)」と呼ばれる地域的枠組みを発足させ、EUや米国等の協力を得ながら、独自のインフラ構築に向けた協力に取り組んでいる。日本は中・東欧諸国への関心を中国からの「引き離し」にのみ限定させるのではなく、これらの国々の真のニーズを十分に理解した上で、ポスト一帯一路の秩序をこれらの国々と共に検討し、構築していく必要がある。その努力こそが、中・東欧諸国と日本の関係を真に多層的なものへと変化させるうえで不可欠といえるであろう。
※1 「16+1」EUに加盟している11カ国(ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、ポーランド、クロアチア、スロベニア、スロバキア、チェコ、リトアニア、ラトビア、エストニア)、そしてEUに未加盟の加盟候補国および潜在的加盟候補国の5カ国(ボスニア=ヘルツェゴビナ、セルビア、北マケドニア、モンテネグロ、アルバニア)の、合計16カ国で2012年に発足した。2019年にギリシャが参加し、参加国が17になったことに伴い、「17+1」と改称された(なお中国側はこれを、「中国-中東欧首脳会議(China-CEEC Summit)」と称している)。しかし本論でも述べるとおり、2021年5月にはリトアニアが「17+1」からの離脱を表明したため、現状の参加国はまた16カ国に戻っている。本論では混乱を避けるため、本来であれば「17+1」と標記すべき2019年4月から2021年5月までの時期に関しても、「16+1」で統一することとする。
※2 Martin Hala, “Europe’s new ‘Eastern Bloc’,” Politico.eu, April 13, 2018; Jame Kynge and Michael Peel, “Brussels rattled as China reaches out to eastern Europe,” Financial Times, November 27, 2017.
※3 東野 篤子「ヨーロッパと一帯一路――脅威認識・落胆・期待の共存」『国際安全保障』47巻1号、2019年。
※4 東野 篤子『中東欧・中国関係の変質と 「17+1」首脳会合』ROLES REPORT No.1 https://roles.rcast.u-tokyo.ac.jp/publication/1
※5 ただし、佐橋亮『米中対立――アメリカの戦略転換と分断される世界』(中公新書、2021年)では、米中対立におけるヨーロッパの立ち位置にも丁寧に触れられている。
※6 Foreign and Commonwealth Office, UK-China Joint Statement on Building a Global Comprehensive Strategic Partnership for the 21st Century, October 22, 2015.
※7 「嫌米と中国依存に揺れるメルケル独首相の花道」『日本経済新聞』2020年8月28日 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63057170W0A820C2000000/
※8 そのハンガリーにおいてでさえ、中国からの多額の借り入れを行ってブダペストに復旦大学を開校するという政府案に対し、国内からの反発が強くなっていることには留意すべきであろう。Panyi, Szabolcs “The Fight Over Fudan: A Chinese University in Budapest Sparks Reckoning for Sino-Hungarian Relations,” 7 June 2021. https://chinaobservers.eu/the-fight-over-fudan-a-chinese-university-in-budapest-sparks-reckoning-for-sino-hungarian-relations/
※9 この指摘については以下を参照。鶴岡路人「イントロダクション 戦略的自律を目指す欧州 試される日本の外交力」『Wedge Report』 2021年1月18日、 January. https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21836
※10 そういった問題意識を反映した日本における報道の一例として、「[社説]日欧連携を地域安定に生かせ」『日本経済新聞』2021年5月28日。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK285140Y1A520C2000000/
※11 東欧革命直後の時期における、日本による対中・東欧諸国支援については、例えば以下の海部俊樹内閣総理大臣の演説(1990年1月9日)を参照。 https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/exdpm/19900109.S1J.html
※12 たとえば、中・東欧地域の中心的存在であるいわゆる「ヴィシェグラード4カ国(V4)」に対してですら、日本の政治家の訪問は限定的であった。2013年6月の安倍首相(当時)のポーランド訪問は、日本の首相としては10年ぶりであった。また、2019年4月の安倍首相(同)のスロバキア訪問は、日本の首相として初めてであった。ハンガリーには1990年に海部俊樹総理が、チェコには2003年に小泉純一郎総理が訪問したのが、それぞれ最後である。
※13 「東欧4カ国と自由な国際秩序で一致 中国にらみ外相会談」『日本経済新聞』2021年5月7日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA077010X00C21A5000000/; 「日本の対中懸念に『強い共感』外相、バルト3国を歴訪」『朝日新聞』2021年7月3日 https://digital.asahi.com/articles/ASP7376NXP73UTFK00D.html
執筆者プロフィール
東野篤子(ひがしの・あつこ)
筑波大学人文社会系准教授
慶應義塾大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院修士課程修了、英国バーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程修了(Ph.D)。広島市立大学准教授などを経て、筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授、専門はヨーロッパ国際政治、国際関係論。共著に『変わりゆくEU
――永遠平和のプロジェクトの行方』明石書店、2020年等。

