
(5) 中国からみたロシア・ウクライナ紛争とそれにかかわる地政学リスク

掲載日:2022年6月3日
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
柯隆
一般的に中国人はロシアという国に対してきわめて複雑な感情を持っている。50代以上の中国人は毛沢東時代(1949-76年)に青春時代を過ごした。当時、外国の文学作品といえば、ほとんどはソ連時代の作品だった。共産党幹部も外国訪問や海外留学といえば、行先はソ連や東欧だった。プーシキンやゴーリキーの作品は当時の中国人に大きな影響を与えた。
しかし、歴史が好きな中国人はウラジオストクをはじめ、中国東北の広大な領土がロシアに略奪されたことを知り、怒りは収まらない。とくに、ソ連時代、中ソはウスリー川中流のダマンスキー島(中国名:珍宝島)の領有権をめぐり、対立し、軍事衝突にまで発展した。筆者も小学校時代、学校でソ連が我が国の国境に100万人の兵士を駐屯させいつでも侵略してくる可能性があると教えられたことを今でも覚えている。50年前、毛沢東はソ連による侵略を心配して、米国に歩み寄り、米中国交回復が実現した。
そして、日中戦争において中ソは抗日という意味では同じ立場だった。しかし、日本軍が追いやられたあと、中国東北部はソ連の占領下に置かれた。のちにソ連軍による虐殺、略奪、婦女暴行などの犯罪行為が明らかになった。その多くは中国の歴史教科書から削除されている。なぜならば、中国政府にとって旧ソ連、そして、今のロシアとの外交関係を維持する必要があったからである。
毛沢東はスターリン時代、ソ連との関係を良好に保つ必要性からスターリンに敬意を表していた。しかし、1953年スターリンが死去したあと、中ソ関係は急速に悪化してしまった。両国関係の悪化を受けて、ソ連政府は中国に対する経済援助を取りやめ、中国に派遣していたエンジニアや技術者をいっせいに帰国させてしまった。以降、中ソは敵対し、毛沢東と周恩来は米国に歩み寄り、外交方針を180度転換させた。
1978年から中国は改革・開放をはじめた。リアリストの鄧小平は経済の自由化を推進し、中国経済に資本主義市場経済の要素を取り入れた。半面、ソ連経済は年を追うごとに困窮していった。米国との軍拡競争に負けたソ連は国内経済が破綻し、最終的にソ連邦は崩壊した。そのなかでウクライナはソ連から独立した。このことはソ連に止まらず、東欧諸国にまで波及して、その多くは民主化してソ連と距離を置くようになった。これは中国共産党に大きなショックを与えた。
中国政府の公式文書においてはソ連の崩壊についてゴルバチョフ書記長(当時)の責任にされている。むろん、それは真実ではない。ソ連の崩壊は社会主義体制の致命傷によるものである。逆に、中国経済が繁栄したのは資本主義市場経済の要素を取り入れたからである。
元紅衛兵たちのDNA
ここまでの整理からも、中国政府と中国人の対ソ連・ロシアの感情がかなり起伏の激しいものであることがわかる。中華人民共和国が成立してからの歴代指導者の経歴をみると、毛沢東は海外での長期滞在歴がなかった。生前、2回ほどソ連を訪問したことがあるが、いずれもスターリン時代だった。鄧小平は若いころ、フランスに留学したことがあるといわれている。どこまで勉強したかは不明だが、フランスに長期滞在したことがあるのは事実である。江沢民と李鵬はソ連に留学したことのある工学系だった。
ここで重要なのは習近平政権のチーム、すなわち、7人の常務委員の経歴である。表1に示したのは習政権の7人の常務委員の誕生と文化大革命が始まった1966年当時の年齢と学年である。全国人民代表大会常務委員長の栗戦書は高校一年生だったほかは、ほとんどが小学生か中学生だった。すなわち、この7人のいずれも元紅衛兵だった。彼らは基礎教育が終了していなかった。なぜならば、文革が開始すると同時に、学校教育がほとんどストップしてしまい、当時の紅衛兵は学校の先生や知識人などを造反有理と叫びながら打倒したからである。
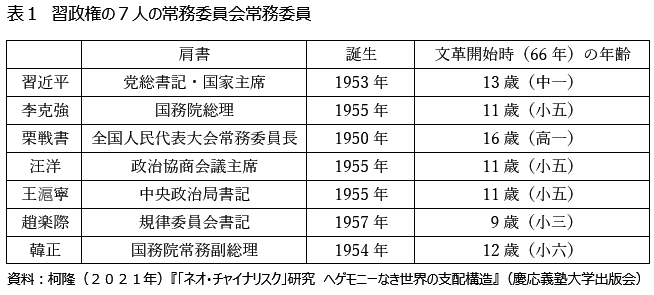
元紅衛兵のDNAには権力崇拝の傾向が強い。しかも、彼らこそソ連文学に強く影響を受けた世代である。元紅衛兵たちは初等教育しか受けておらず、とくに歴史教育は皆無だった。毛時代の歴史教育で教えたのは歴史の事実(史実)ではなく、政治教育の必要性に応じた恣意的な捏造に基づいたユートピアだった。そのなかでソ連との関係に関する記述はとくに史実に反する記述が多く、一方的にレーニン主義の闘争理論が強調され、元紅衛兵の若者たちは強く影響を受けてしまった。
毛時代に育った元紅衛兵たちのもう一つの特質は遵法精神の欠如である。そもそも文化大革命は毛が自らの経済政策失敗の責任を逃れるために引き起こしたもので、その直接の目的である党内最大の政敵だった劉少奇国家主席(当時)を打倒するため、紅衛兵たちが利用された。紅衛兵たちの迫害を受けた劉は憲法の小冊子を手に、「紅衛兵のみなさん、私は国家主席でも、基本的な人権がある」と主張した。それに対して、紅衛兵たちは「革命無罪、造反有理」と返した。結果的に劉は紅衛兵たちに迫害され惨殺されてしまった。
問題は中国で文化大革命に対する反省がいまだになされていないことにある。習政権が誕生してから、習主席は文化大革命を「歴史的に困難な模索」と定義した。文革の出発点は共産党内部の権力闘争だったが、たちまち文化人を迫害する若者を中心とする大衆運動に発展してしまった。たくさんの知識人が迫害され殺された。それにより中国の古典文化が粉々に破壊されてしまった。
プーチンロシアとの価値観の共有
中国共産党にとってソ連邦の崩壊は間違いなく青天の霹靂だった。なぜならば、ソ連共産党は中国共産党にとって師匠のような存在だったからである。鄧小平などの長老からみれば、ゴルバチョフ書記長(当時)は間違いなく共産主義の裏切り者だった。政治学者の分析によれば、プーチン大統領は共産主義のイデオロギーに固執しないが、偉大なるロシア帝国を取り戻そうとしているといわれている。国土を拡張しようとする点について習政権と完全に一致している。
むろん、国運が高まる局面において政治指導者が国土を拡張させようとする考えはいつの時代も変わらない。西洋諸国の植民地政策はその好例といえる。問題はやり方に違いがある。ロシア人の特性に明るい研究者によると、ロシア人はなにか目的を達成しようとするとき、往々にして相手に恐怖心を与え怖がらせようとする。すなわち、力で相手を従わせるのはロシア流のやり方であるといわれている。この描写が正しければ、ロシアによるウクライナ侵攻について理解しやすいはずである。
このことについてロシアとよく似ているのは習政権の戦狼外交である。戦狼外交とは戦う外交のことである。すなわち、相手と妥協せず、力で勝負するやり方である。2018年、米トランプ政権は米中貿易不均衡を理由に中国に対して貿易制裁を発動して米中貿易戦争にまで発展した。そのときに習主席は国内で行う演説で中国の文化について「目には目、歯には歯」と強調した。すなわち、米国に絶対に妥協しないということである。その後、米中対立は日増しにエスカレートしていった。
本来ならば、貿易不均衡が原因で米中貿易摩擦が起きたことを考えれば、その貿易不均衡の原因を米中双方で調査して原因を特定できるはずである。それによって米中貿易戦争が避けられたはずだった。
外交の基本は相手に恐怖心を与えるのではなく、相手に好かれ尊敬されるように努力することである。ウクライナ戦争が正義の戦争かどうかは別として、プーチン大統領はウクライナを併合しようとするならば、ウクライナと友好な関係を保つことが重要であった。ウクライナをネオナチと称して武力行使して侵攻するやり方は明らかに逆効果になる。残念ながら、この簡単な理屈がプーチン大統領およびその側近には分かっていないようだ。
ロシア政府の関係者は、ロシアが窮地に追い込まれているのは西側諸国による情報封鎖と情報操作によるものと主張している。要するに、ロシアのウクライナ侵略は捏造されたもので、ロシアはウクライナ人民をネオナチから解放するために戦っていると言うのだが、滑稽な詭弁でそれを信じるものはほとんどいないはずである。
それについて、中国政府はどういう見方をしているのだろうか。米中対立が先鋭化している現実から、中国にとってロシアとの友好関係を維持するのはなによりも重要である。しかし、ことはそれほど単純ではない。なぜならば、中国はこれまでのところ、ウクライナから空母を輸入し、戦闘機の技術を習得している。ウクライナ戦争が起きたときに、6000人もの中国人留学生とビジネス関係者はウクライナに滞在していた。中国政府にとってロシアかウクライナかの選択は難しいものである。だからこそ、中国外交部報道官はいつも曖昧な答弁をしている。中国政府はいかなる国に対しても国土保全の主権を支持するとしながらも、ロシアのウクライナ侵攻を侵略といわない。
アメリカをはじめとするNATO諸国は再三にわたって、中国に「ロシアに支援したら、必ず代償を払わせる」と警告している。ことの重大さは中国も理解していて、表向きはロシアに対する支援を行っていない。ただし、ロシアとの一般貿易は止めていない。ロシアは最先端の軍事技術を持っているようだが、裾野産業が弱く、民生産業はとくにぼろぼろな状態にある。ロシア経済は石油、天然ガスと食糧を輸出して、海外から民生用の日用品を大量に輸入する。ウクライナ戦争が起きてから、西側諸国はロシアに対する経済制裁を実施して、ロシア経済に予想以上のダメージを与えている。
軍事専門家によれば、プーチン大統領およびその側近は当初、ウクライナを長くても数日間で攻略でき、ゼレンスキー政権に代わる傀儡政権を樹立して、ウクライナを手に入れることができるとみていたといわれている。しかし、ウクライナ軍の抵抗は予想以上に強く、西側諸国は直接参戦していないが、ウクライナに対する軍事支援は迅速かつ強力なものだった。結局、2か月以上経過しても、ロシアはウクライナを攻略できていない。なによりも、ロシア自身は国際社会で孤立してしまっている。
習政権の打算
そもそも中国はロシアと同じボートに乗っている仲間ではない。アメリカに対抗するという立場において利益を共有できるが、中国経済はハイテク技術を中心に日米欧に依存している。中国にとって米中ディカップリング(分断)は悲劇を意味するものである。すなわち、中国は産業構造の高度化を実現できず、経済は急減速していく可能性が高い。
結論的にいえば、習政権はロシアとの連携を維持しながらも、アメリカとの関係をこれ以上拗らせないように気を付けないといけない。同時に、ロシアとの連携が重要だが、適切な距離を保つことが重要である。その距離が遠すぎると、近い将来、中国が台湾に侵攻した場合、間違いなく西側諸国から加えられる制裁に対して、ロシアにバックアップを頼めなくなる。しかし、その距離が近すぎると、中国はロシアとともに国際社会で孤立してしまうおそれがある。まさに合従連衡のゲームである。
実はロシアのウクライナ侵攻は習主席に大きなショックを与えている可能性が高い。習政権は自らの正当性を証明するために、一日も早く台湾を併合したい。中国はアメリカやヨーロッパから軍事技術を輸入できない。中国の軍事技術のほとんどはロシアに頼っている。そのロシアは陸続きのウクライナに侵攻しても、なかなか攻略できていない。中国人民解放軍は台湾に侵攻する場合、台湾海峡を渡らなければならない。台湾はアメリカから最先端の戦闘機を輸入し保有している。現状のままでは、人民解放軍が台湾に侵攻しても、攻略できない可能性が高い。このことは習主席にとってもっとも歯がゆい結果になる。すなわち、手に入れたいが、手に入らない。表2に示したのは台湾とウクライナの経済力と軍事力の比較である。
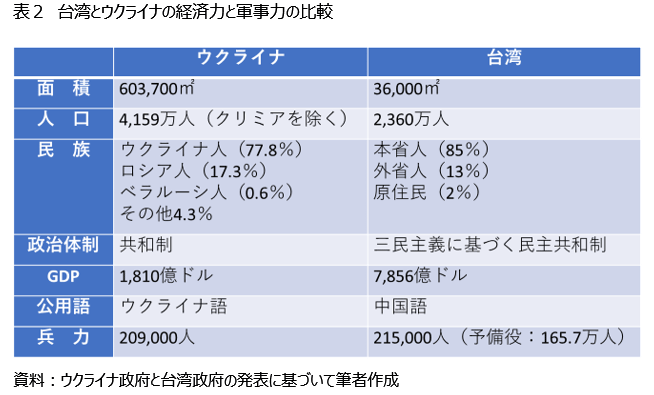
戦争するにはお金がかかる。軍事の専門家によると、ロシアのウクライナ侵攻は1日あたり数億ドルかかるといわれている。しかも外国資本は相次いでロシアを離れている。だからこそロシアのウクライナ侵攻はロシアの失敗に終わる可能性が高い。
同様に、中国も同じ問題に直面するはずである。確かに中国の経済規模は名目GDPについては世界二番目だが、ハイテク製品と商品の輸出は主に中国に進出している多国籍企業によるものである。外国資本がもっとも嫌うのはリスクである。人民解放軍が台湾に侵攻した場合、まず台湾企業は中国を離れる。それと同時に、日米欧の多国籍企業とその部品メーカーなども中国を離れるだろう。中国は技術を失うだけでなく、雇用機会も喪失してしまう。中国の富裕層は大挙して金融資産をアメリカやタックスヘイブンに逃避させる。つまり世界二番目の経済といえども、あっという間に空洞化してしまう可能性が高い。何よりも習政権にとって不利なのは中国経済が今、急減速していることである。中国の立場に立って合理的に判断すれば、このままでは、台湾に侵攻できない。
むろん、強権政治の指導者がつねに合理的に判断できるかは不明である。今回のウクライナ戦争も合理的に考えれば、プーチン大統領は侵攻を決断しないはずだった。一部の政治学者はプーチン大統領が側近の間違った情報に騙されたと指摘している。その可能性は排除できないが、それよりもこの難局をもたらしたのはだれかがプーチン大統領を騙したからではなく、強権政治の致命傷によるものといったほうがよかろう。
同様に、合理的に考えれば、習主席は台湾侵攻を決断しないはずである。しかし、プーチン大統領と同じように強権政治の致命傷により間違った決断を行う可能性を完全に排除できない。重要なのはそれに伴う地政学リスクを管理することである。リスクというのは絶対に起きないと考えるのではなく、その可能性を念頭に危機に備えておくことが重要である。
執筆者プロフィール
柯 隆(か・りゅう) Long Ke
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
1963年、中華人民共和国・江蘇省南京市生まれ。88年来日、愛知大学法経学部入学。92年、同大卒業。94年、名古屋大学大学院修士課程修了(経済学修士号取得)。長銀総合研究所国際調査部研究員(98年まで)。98~2006年、富士通総研経済研究所主任研究員、06年より同主席研究員を経て、現職。 兼職:静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、多摩大学大学院客員教授、研究分野・主な関心領域:開発経済、中国のマクロ経済
著書:『「ネオ・チャイナリスク」研究:ヘゲモニーなき世界の支配構造』(慶應義塾大学出版会、2021)、『中国「強国復権」の条件』(慶應義塾大学出版会、2018。第13回 樫山純三賞)ほか。
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
柯隆
一般的に中国人はロシアという国に対してきわめて複雑な感情を持っている。50代以上の中国人は毛沢東時代(1949-76年)に青春時代を過ごした。当時、外国の文学作品といえば、ほとんどはソ連時代の作品だった。共産党幹部も外国訪問や海外留学といえば、行先はソ連や東欧だった。プーシキンやゴーリキーの作品は当時の中国人に大きな影響を与えた。
しかし、歴史が好きな中国人はウラジオストクをはじめ、中国東北の広大な領土がロシアに略奪されたことを知り、怒りは収まらない。とくに、ソ連時代、中ソはウスリー川中流のダマンスキー島(中国名:珍宝島)の領有権をめぐり、対立し、軍事衝突にまで発展した。筆者も小学校時代、学校でソ連が我が国の国境に100万人の兵士を駐屯させいつでも侵略してくる可能性があると教えられたことを今でも覚えている。50年前、毛沢東はソ連による侵略を心配して、米国に歩み寄り、米中国交回復が実現した。
そして、日中戦争において中ソは抗日という意味では同じ立場だった。しかし、日本軍が追いやられたあと、中国東北部はソ連の占領下に置かれた。のちにソ連軍による虐殺、略奪、婦女暴行などの犯罪行為が明らかになった。その多くは中国の歴史教科書から削除されている。なぜならば、中国政府にとって旧ソ連、そして、今のロシアとの外交関係を維持する必要があったからである。
毛沢東はスターリン時代、ソ連との関係を良好に保つ必要性からスターリンに敬意を表していた。しかし、1953年スターリンが死去したあと、中ソ関係は急速に悪化してしまった。両国関係の悪化を受けて、ソ連政府は中国に対する経済援助を取りやめ、中国に派遣していたエンジニアや技術者をいっせいに帰国させてしまった。以降、中ソは敵対し、毛沢東と周恩来は米国に歩み寄り、外交方針を180度転換させた。
1978年から中国は改革・開放をはじめた。リアリストの鄧小平は経済の自由化を推進し、中国経済に資本主義市場経済の要素を取り入れた。半面、ソ連経済は年を追うごとに困窮していった。米国との軍拡競争に負けたソ連は国内経済が破綻し、最終的にソ連邦は崩壊した。そのなかでウクライナはソ連から独立した。このことはソ連に止まらず、東欧諸国にまで波及して、その多くは民主化してソ連と距離を置くようになった。これは中国共産党に大きなショックを与えた。
中国政府の公式文書においてはソ連の崩壊についてゴルバチョフ書記長(当時)の責任にされている。むろん、それは真実ではない。ソ連の崩壊は社会主義体制の致命傷によるものである。逆に、中国経済が繁栄したのは資本主義市場経済の要素を取り入れたからである。
元紅衛兵たちのDNA
ここまでの整理からも、中国政府と中国人の対ソ連・ロシアの感情がかなり起伏の激しいものであることがわかる。中華人民共和国が成立してからの歴代指導者の経歴をみると、毛沢東は海外での長期滞在歴がなかった。生前、2回ほどソ連を訪問したことがあるが、いずれもスターリン時代だった。鄧小平は若いころ、フランスに留学したことがあるといわれている。どこまで勉強したかは不明だが、フランスに長期滞在したことがあるのは事実である。江沢民と李鵬はソ連に留学したことのある工学系だった。
ここで重要なのは習近平政権のチーム、すなわち、7人の常務委員の経歴である。表1に示したのは習政権の7人の常務委員の誕生と文化大革命が始まった1966年当時の年齢と学年である。全国人民代表大会常務委員長の栗戦書は高校一年生だったほかは、ほとんどが小学生か中学生だった。すなわち、この7人のいずれも元紅衛兵だった。彼らは基礎教育が終了していなかった。なぜならば、文革が開始すると同時に、学校教育がほとんどストップしてしまい、当時の紅衛兵は学校の先生や知識人などを造反有理と叫びながら打倒したからである。
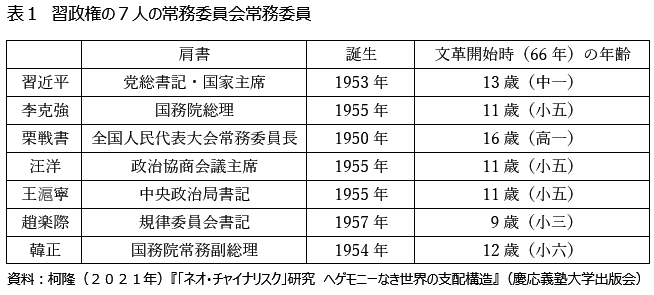
元紅衛兵のDNAには権力崇拝の傾向が強い。しかも、彼らこそソ連文学に強く影響を受けた世代である。元紅衛兵たちは初等教育しか受けておらず、とくに歴史教育は皆無だった。毛時代の歴史教育で教えたのは歴史の事実(史実)ではなく、政治教育の必要性に応じた恣意的な捏造に基づいたユートピアだった。そのなかでソ連との関係に関する記述はとくに史実に反する記述が多く、一方的にレーニン主義の闘争理論が強調され、元紅衛兵の若者たちは強く影響を受けてしまった。
毛時代に育った元紅衛兵たちのもう一つの特質は遵法精神の欠如である。そもそも文化大革命は毛が自らの経済政策失敗の責任を逃れるために引き起こしたもので、その直接の目的である党内最大の政敵だった劉少奇国家主席(当時)を打倒するため、紅衛兵たちが利用された。紅衛兵たちの迫害を受けた劉は憲法の小冊子を手に、「紅衛兵のみなさん、私は国家主席でも、基本的な人権がある」と主張した。それに対して、紅衛兵たちは「革命無罪、造反有理」と返した。結果的に劉は紅衛兵たちに迫害され惨殺されてしまった。
問題は中国で文化大革命に対する反省がいまだになされていないことにある。習政権が誕生してから、習主席は文化大革命を「歴史的に困難な模索」と定義した。文革の出発点は共産党内部の権力闘争だったが、たちまち文化人を迫害する若者を中心とする大衆運動に発展してしまった。たくさんの知識人が迫害され殺された。それにより中国の古典文化が粉々に破壊されてしまった。
プーチンロシアとの価値観の共有
中国共産党にとってソ連邦の崩壊は間違いなく青天の霹靂だった。なぜならば、ソ連共産党は中国共産党にとって師匠のような存在だったからである。鄧小平などの長老からみれば、ゴルバチョフ書記長(当時)は間違いなく共産主義の裏切り者だった。政治学者の分析によれば、プーチン大統領は共産主義のイデオロギーに固執しないが、偉大なるロシア帝国を取り戻そうとしているといわれている。国土を拡張しようとする点について習政権と完全に一致している。
むろん、国運が高まる局面において政治指導者が国土を拡張させようとする考えはいつの時代も変わらない。西洋諸国の植民地政策はその好例といえる。問題はやり方に違いがある。ロシア人の特性に明るい研究者によると、ロシア人はなにか目的を達成しようとするとき、往々にして相手に恐怖心を与え怖がらせようとする。すなわち、力で相手を従わせるのはロシア流のやり方であるといわれている。この描写が正しければ、ロシアによるウクライナ侵攻について理解しやすいはずである。
このことについてロシアとよく似ているのは習政権の戦狼外交である。戦狼外交とは戦う外交のことである。すなわち、相手と妥協せず、力で勝負するやり方である。2018年、米トランプ政権は米中貿易不均衡を理由に中国に対して貿易制裁を発動して米中貿易戦争にまで発展した。そのときに習主席は国内で行う演説で中国の文化について「目には目、歯には歯」と強調した。すなわち、米国に絶対に妥協しないということである。その後、米中対立は日増しにエスカレートしていった。
本来ならば、貿易不均衡が原因で米中貿易摩擦が起きたことを考えれば、その貿易不均衡の原因を米中双方で調査して原因を特定できるはずである。それによって米中貿易戦争が避けられたはずだった。
外交の基本は相手に恐怖心を与えるのではなく、相手に好かれ尊敬されるように努力することである。ウクライナ戦争が正義の戦争かどうかは別として、プーチン大統領はウクライナを併合しようとするならば、ウクライナと友好な関係を保つことが重要であった。ウクライナをネオナチと称して武力行使して侵攻するやり方は明らかに逆効果になる。残念ながら、この簡単な理屈がプーチン大統領およびその側近には分かっていないようだ。
ロシア政府の関係者は、ロシアが窮地に追い込まれているのは西側諸国による情報封鎖と情報操作によるものと主張している。要するに、ロシアのウクライナ侵略は捏造されたもので、ロシアはウクライナ人民をネオナチから解放するために戦っていると言うのだが、滑稽な詭弁でそれを信じるものはほとんどいないはずである。
それについて、中国政府はどういう見方をしているのだろうか。米中対立が先鋭化している現実から、中国にとってロシアとの友好関係を維持するのはなによりも重要である。しかし、ことはそれほど単純ではない。なぜならば、中国はこれまでのところ、ウクライナから空母を輸入し、戦闘機の技術を習得している。ウクライナ戦争が起きたときに、6000人もの中国人留学生とビジネス関係者はウクライナに滞在していた。中国政府にとってロシアかウクライナかの選択は難しいものである。だからこそ、中国外交部報道官はいつも曖昧な答弁をしている。中国政府はいかなる国に対しても国土保全の主権を支持するとしながらも、ロシアのウクライナ侵攻を侵略といわない。
アメリカをはじめとするNATO諸国は再三にわたって、中国に「ロシアに支援したら、必ず代償を払わせる」と警告している。ことの重大さは中国も理解していて、表向きはロシアに対する支援を行っていない。ただし、ロシアとの一般貿易は止めていない。ロシアは最先端の軍事技術を持っているようだが、裾野産業が弱く、民生産業はとくにぼろぼろな状態にある。ロシア経済は石油、天然ガスと食糧を輸出して、海外から民生用の日用品を大量に輸入する。ウクライナ戦争が起きてから、西側諸国はロシアに対する経済制裁を実施して、ロシア経済に予想以上のダメージを与えている。
軍事専門家によれば、プーチン大統領およびその側近は当初、ウクライナを長くても数日間で攻略でき、ゼレンスキー政権に代わる傀儡政権を樹立して、ウクライナを手に入れることができるとみていたといわれている。しかし、ウクライナ軍の抵抗は予想以上に強く、西側諸国は直接参戦していないが、ウクライナに対する軍事支援は迅速かつ強力なものだった。結局、2か月以上経過しても、ロシアはウクライナを攻略できていない。なによりも、ロシア自身は国際社会で孤立してしまっている。
習政権の打算
そもそも中国はロシアと同じボートに乗っている仲間ではない。アメリカに対抗するという立場において利益を共有できるが、中国経済はハイテク技術を中心に日米欧に依存している。中国にとって米中ディカップリング(分断)は悲劇を意味するものである。すなわち、中国は産業構造の高度化を実現できず、経済は急減速していく可能性が高い。
結論的にいえば、習政権はロシアとの連携を維持しながらも、アメリカとの関係をこれ以上拗らせないように気を付けないといけない。同時に、ロシアとの連携が重要だが、適切な距離を保つことが重要である。その距離が遠すぎると、近い将来、中国が台湾に侵攻した場合、間違いなく西側諸国から加えられる制裁に対して、ロシアにバックアップを頼めなくなる。しかし、その距離が近すぎると、中国はロシアとともに国際社会で孤立してしまうおそれがある。まさに合従連衡のゲームである。
実はロシアのウクライナ侵攻は習主席に大きなショックを与えている可能性が高い。習政権は自らの正当性を証明するために、一日も早く台湾を併合したい。中国はアメリカやヨーロッパから軍事技術を輸入できない。中国の軍事技術のほとんどはロシアに頼っている。そのロシアは陸続きのウクライナに侵攻しても、なかなか攻略できていない。中国人民解放軍は台湾に侵攻する場合、台湾海峡を渡らなければならない。台湾はアメリカから最先端の戦闘機を輸入し保有している。現状のままでは、人民解放軍が台湾に侵攻しても、攻略できない可能性が高い。このことは習主席にとってもっとも歯がゆい結果になる。すなわち、手に入れたいが、手に入らない。表2に示したのは台湾とウクライナの経済力と軍事力の比較である。
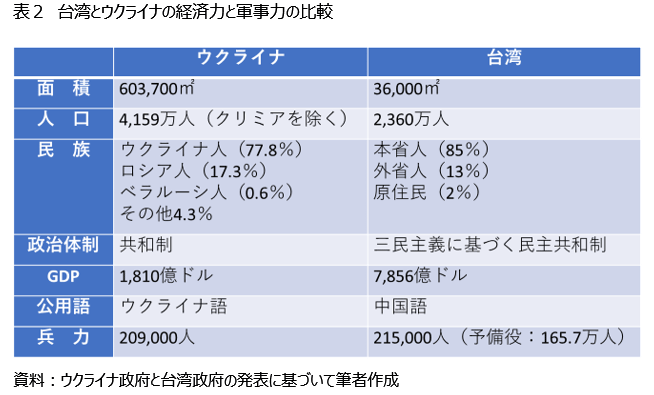
戦争するにはお金がかかる。軍事の専門家によると、ロシアのウクライナ侵攻は1日あたり数億ドルかかるといわれている。しかも外国資本は相次いでロシアを離れている。だからこそロシアのウクライナ侵攻はロシアの失敗に終わる可能性が高い。
同様に、中国も同じ問題に直面するはずである。確かに中国の経済規模は名目GDPについては世界二番目だが、ハイテク製品と商品の輸出は主に中国に進出している多国籍企業によるものである。外国資本がもっとも嫌うのはリスクである。人民解放軍が台湾に侵攻した場合、まず台湾企業は中国を離れる。それと同時に、日米欧の多国籍企業とその部品メーカーなども中国を離れるだろう。中国は技術を失うだけでなく、雇用機会も喪失してしまう。中国の富裕層は大挙して金融資産をアメリカやタックスヘイブンに逃避させる。つまり世界二番目の経済といえども、あっという間に空洞化してしまう可能性が高い。何よりも習政権にとって不利なのは中国経済が今、急減速していることである。中国の立場に立って合理的に判断すれば、このままでは、台湾に侵攻できない。
むろん、強権政治の指導者がつねに合理的に判断できるかは不明である。今回のウクライナ戦争も合理的に考えれば、プーチン大統領は侵攻を決断しないはずだった。一部の政治学者はプーチン大統領が側近の間違った情報に騙されたと指摘している。その可能性は排除できないが、それよりもこの難局をもたらしたのはだれかがプーチン大統領を騙したからではなく、強権政治の致命傷によるものといったほうがよかろう。
同様に、合理的に考えれば、習主席は台湾侵攻を決断しないはずである。しかし、プーチン大統領と同じように強権政治の致命傷により間違った決断を行う可能性を完全に排除できない。重要なのはそれに伴う地政学リスクを管理することである。リスクというのは絶対に起きないと考えるのではなく、その可能性を念頭に危機に備えておくことが重要である。
執筆者プロフィール
柯 隆(か・りゅう) Long Ke
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
1963年、中華人民共和国・江蘇省南京市生まれ。88年来日、愛知大学法経学部入学。92年、同大卒業。94年、名古屋大学大学院修士課程修了(経済学修士号取得)。長銀総合研究所国際調査部研究員(98年まで)。98~2006年、富士通総研経済研究所主任研究員、06年より同主席研究員を経て、現職。 兼職:静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、多摩大学大学院客員教授、研究分野・主な関心領域:開発経済、中国のマクロ経済
著書:『「ネオ・チャイナリスク」研究:ヘゲモニーなき世界の支配構造』(慶應義塾大学出版会、2021)、『中国「強国復権」の条件』(慶應義塾大学出版会、2018。第13回 樫山純三賞)ほか。

