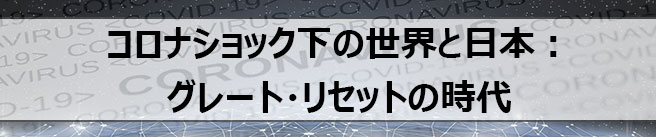コロナショック下の世界と日本:グレート・リセットの時代 (19) 「自国の危機」としての新型コロナ対応 東京都立大学 教授 詫摩 佳代【2021/9/6】
掲載日:2021年9月6日
東京都立大学 教授
詫摩 佳代
はじめに
新型コロナウイルスの感染拡大がパンデミックであるとの認識が示されてからまもなく1年半が経過しようとしているが、感染力の強い変異株の登場もあり、ウイルスとの闘いはいまだに続いている。このウイルスとの闘いにおいて、有力な武器であるのがワクチンだが、そのアクセスには先進国と途上国の間で大きな格差が存在する。2021年8月時点で、少なくとも1回ワクチン接種した人の割合はカナダで73%、イギリスで70%と先進国で軒並み高水準を達成しているのに対して、約13億の人口を抱えるアフリカではたったの1.5%にとどまっている。先進国では追加接種にむけた動きも進んでおり、このままだとアフリカでの接種率は年末までに10%にも届かないだろうという見積もりも出ている。
ワクチンへのアクセス格差は、経済の回復を遅らせることにもつながる。国連開発計画(UNDP)と世界保健機関(WHO)、オックスフォード大らは、中・低所得国がもし高所得国と同程度のワクチン接種率を達成できていたなら、2021年度の中・低所得国のGDP予測は現状を380億ドルほど上回るものだっただろうとの見積もりを発表している。このほかにも多くの研究機関が、ワクチンの不公平なアクセスが感染収束を遅らせ、より大きな経済的コストをもたらすだろうとの試算を発表している。地球全体の危機として対応した方が互いに利得が大きいことを示す客観的なデータが出ているにもかかわらず、国際社会は新型コロナに対して、適切に協力できていない現状である。
それはなぜだろうか?もちろん、世界政府が存在しない中で、各国を協力に向けて強制する術はなく、協力できないのは致し方ないとの見方もできる。他方、歴史を振り返ってみると、そのような中でも、国々は感染症に対して比較的容易に協力を進めてきた経緯がある。また最近では、エイズやエボラ出血熱への対応に関して、国際社会の平和と安全への危機だという認識にたち、先進国が率先してハイレベルな対応が行われてきた。そうした前例とは対照的に、なぜ新型コロナをめぐって協力が容易でないのだろうか。本稿ではこの問いを読み解いていきたい。
感染症へのハイレベル対応
国境を跨ぐ感染症への対応は、概ね国際協調に支えられてきた。理由は単純、協力した方が各国にとって、管理に必要な情報やツールが多く得られるからだ。実際、第一次世界大戦前の独仏、第二次世界大戦前の日本と国際社会、そして冷戦期の米ソはその政治的対立にもかかわらず、感染症に関して協力した。また近年では、感染症へのハイレベル対応も頻繁にみられてきた。グローバル化が進展した国際社会において、感染症は瞬く間に広がり、我々の健康に限らず、経済や社会機能など他分野に影響を及ぼすグローバルな危機につながりうるからだ。こうした認識の浸透に伴い、感染症は公衆衛生という閉じられた領域から、安全保障をも含む広義の文脈の中で位置づけ直されてきたのである。
その顕著な事例がエイズである。1981年に初の症例が報告されて以降、世界を席巻してきたエイズであるが、感染者数は1996年にピークを迎えたとはいえ、2019年時点で約3800万人いると推定されている。2000年1月の国連安保理では、エイズの感染拡大がアフリカでの国連平和維持活動(PKO)の展開など、国際平和の維持においても打撃を与えうるとの認識にたち、安全保障の観点からエイズ対策の必要性を指摘した安保理決議1308が採択された。この頃から、先進国首脳会議(サミット)でもエイズやマラリアなどの感染症が議題となってきた。
2014年の西アフリカでのエボラ出血熱の流行に際しては、当時のオバマ米大統領のイニシアティブのもと、国連でサミットが開催され、世界規模の危機に対応するための話し合いが行われた。国連安保理ではエボラの流行が国際社会の平和と安全への脅威になりうると謳った安保理決議2177が採択され、その後、国連エボラ緊急対応ミッションが設立され、リベリアで展開されていた国連平和維持活動と協力しながら対応にあたった。総じて、近年の世界的な感染症に対しては、そのインパクトが広範囲に及ぶからこそ、安全保障の観点からハイレベルな対応がなされてきた。
「自国の危機」としての新型コロナ対応
新型コロナも健康に限らず、世界経済や世界的な貧困の動向等にすでに多大なインパクトをもたらしてきた。それにもかかわらずエイズやエボラとは異なり、ハイレベルな対応は伴っていない。2020年7月の国連安保理では安保理決議2532が採択されたものの、その内容は、コロナ禍における国際紛争に関するものであり、エボラ時のように国際協力によって感染そのものを収束させようという内容ではなかった。
新型コロナとそれ以前の感染症を大きく隔てるものは、世界同時多発的にこのウイルスが広がり、対応のためのリソースをめぐって、またこの禍をもたらした根源や責任の所在について、各国間で競合や対立が起きているという事実だ。もちろんその背景として、コロナ前から指摘されていた、リベラルな国際秩序の衰退も大いに関係しているが、世界同時多発的という、危機の特異性も大きく影響している。エイズやエボラの時には、被害国がある程度限定されており、そうでない国々を中心に、脅威に対する手段―資金や医療スタッフ、軍隊までも―が動員され、被害国に派遣された。他方、時同じくして、ほぼ全ての国が被害国となり、さらにその闘いの手段となる医療用品やワクチンを開発・製造できる能力が一部の国に限られ、その確保をめぐって各国の競合が起きたのである。
アメリカのトランプ前大統領は早期からワクチン開発に多額の資金を投じ、その際、生産量に限りがあることを見越して、投資の見返りとして米国民分のワクチンを優先的に確保しようとした。また当初、途上国向けワクチンを製造していたインドでは、感染爆発が起きた2021年4月以降、国内で製造するワクチンを全て国内向けとし、輸出禁止の措置を講じた。総じて、世界同時多発的な新型コロナ危機に際しては、各国が「自国の危機」として捉える視点が先行し、エボラやエイズの時のように「国際社会の危機」という視点を持ち合わせることができない、あるいは持っていたとしても、前面に打ち出すことができず、結果的に地球規模でこのウイルスに適切に対処することが叶わなくなっているのである。
政治としての新型コロナ対応
各国が「自国の危機」として新型コロナを捉えるということは、上述の通り、国家間でリソースの確保やその起源、責任の所在等に関して、競合や対立を引き起こすこととなった。結果、新型コロナ対応は極めて政治的な側面を持ち合わせることとなった。顕著な事例は米中間に見られた。まだアメリカで感染がほとんど見られなかった2020年2月初旬、習近平国家主席と電話会談した際には当時のトランプ米大統領は「中国政府が素晴らしい統制を示している」と評価、またその直後のツイッターへの投稿で「われわれは中国を助けるために緊密に協力している」と述べていた。
しかし2020年3月以降、米国で感染者数が劇的に増加すると、秋に控えていた大統領選挙を意識して、新型コロナを「武漢ウイルス」と呼んだり、「中国寄り」とみなすWHOへの批判を強めることで、政権批判を回避しようと試みた。他方、中国は中南米や中東、東南アジアなど、ワクチン開発・製造能力を持たない国に対して、積極的に自国産ワクチンを販売、提供し、あるいは製造支援を行うことで、その見返りとして政治的影響力の拡大を目指してきた。
対応の政治化という側面は国家間のみならず、各国内レベルでも見られてきた。新型コロナウイルスは接触、飛沫、マイクロ飛沫といった経路で感染するため、その感染制御において、人との接触をある程度断つ必要がある。そのため、多くの国でロックダウンや飲食店・商業施設の休業や時短営業などの措置が講じられたが、当然のことながら、そのような策には莫大な経済的社会的ダメージを伴った。ウイルスとの闘いが長期化すればするほど、各国の為政者たちは感染拡大を抑えつつも、経済、社会活動へのダメージを極力抑えるという相容れない任務を両立させる必要に迫られた。日本でも、医療関係者からは医療が逼迫しているので、ロックダウンや緊急事態宣言を求める声が叫ばれ、一方、長く休業要請や時短要請を受けてきた事業主からは、これ以上対応できないという悲痛な声も多く叫ばれた。新型コロナ対応には並立不可能な、様々な要望を調整する任務が課せられ、その対応は極めて政治的なものとなった。政治の争点と化した。
今後の展望
残念ながらこのウイルスとの闘いはまだ続きそうだ。ワクチン接種完了者が感染する「ブレイクスルー感染」の報告が増え始める中、日本をはじめとする多くの先進国が追加接種に向けて新たなワクチン供給契約を結んできた。このような中、今までとは異なるスピードで、ワクチンの増産に向けた努力が伴わなければ、ワクチンアクセスの格差はますます拡大すると予測される。世界のどこかで感染が続く限り、ウイルスは変異し続け、各国の自国よがりな政策とウイルスのイタチごっこという悪循環が続くことになる。もちろん、どの国にとっても、危機に際し、自国民の安全や健康を確保しようというのは、国家として当然の行動である。その上で、この悪循環を断ち切るために、何がなされるべきだろうか。短期的な展望と、中長期的な展望に分けて考えてみたい。
まず、短期的な展望についてであるが、先進国による追加接種と途上国での2回接種を両立できるレベルにまで、ワクチンを増産できる体制を早急に整える必要がある。世界貿易機関(WTO)では昨年来、インドと南アフリカが中心となって、新型コロナワクチン特許権放棄が提案されてきたが、先進国の多くが反対しており、特許権放棄を近々実現することは厳しそうだ。高度な技術を要する新型コロナワクチンの製造には、特許権放棄ではなく、むしろ製薬会社のボランタリーな協力を取り付け、技術移転、途上国現地での生産協力、支援というのが現実的だとの見方もある。
米ファイザーとドイツのビオンテックは2021年7月に、南アフリカでワクチン製造を開始すると発表、2022年度からアフリカ専用の生産工場として稼働し、年間1億回分の生産を目指すとしている。このほか、アストラゼネカ社のワクチンはインドや韓国、日本等でライセンス生産が行われてきた。今年下半期には、サノフィやノババックスによる組み替えタンパク質ワクチンの活用も始まり、ワクチン供給量拡大に期待が集まるが、既存のワクチンの生産拡大に向けた努力も製薬会社と先進国の主導により、継続して行われる必要があるだろう。
より長期的な視点としては、感染症への対応を、複数レベルでの安全保障の問題と位置付け直し、制度化していく必要があるだろう。国レベルでは水際対策やワクチンの開発・製造能力の見直し等の必要性が今回の危機を通じて明らかとなった。グローバルなレベルでも、WHOのガバナンスの問題や、国際保健規則(IHR2005)の不備が明らかとなった。既存の枠組みの改定・補強に加え、パンデミックへの包括的な対応枠組みとして、現在提案されている「パンデミック条約」の成立を目指すべきだろう。
地域レベルでも備えを見直す必要がある。新型コロナ対応をめぐって、グローバルなレベルでの協力に関する様々な綻びが明らかになったからこそ、地域レベルでの協力を見直す動きが活性化している。EUは従来、公衆衛生分野の域内協力に積極的ではなかったが、2020年秋に欧州保健連合(European Health Union)の設立に向けて舵を切り始めた。域内での医薬品や医療機器の供給状況のモニタリング、ワクチン治験に関するコーディネート、サーベイランスシステムの整備、加盟国内で病床使用率や医療従事者数など、データの共有等を通じて、公衆衛生上の危機に対する地域レベルでの備えと対応を強化する狙いがある。アフリカでも新型コロナを契機として、地域内協力の重要性が再認識されてきた。
他方、アジアでは、日韓関係の緊張の高まりや、米中対立等を反映する形で、断片的な動き―日中韓ではほとんど進展がない一方、日本とASEAN諸国の間では、ASEAN感染症センターの設置に向けて動きが進展するなど―は見せているが、包括的な地域協力の整備には程遠い現状である。近年多くの新興感染症がアジアで発生していることを踏まえれば、この地域において、近隣諸国間の情報共有や起こりうる感染症に対して治療薬やワクチンの共同開発を行ったり、緊急時の渡航制限や医療用品・医薬品の供給網についてある程度の仕組みを整えることが望ましいことは言うまでもない。日本の国立感染症研究所と中国疾病対策予防センター(中国CDC)、韓国疾病予防管理庁(KDCA)の間には定期的な研究交流が行われており、このような研究者レベルで非公式の協力を積み上げ、いずれ地域内の何らかの包括的な枠組みにつなげていくことも一つの方法ではなかろうか。
感染症は一旦感染が広がれば、各国それぞれにとっての脅威であるが、より巨視的に見れば、地域にとっても、そして国際社会の平和と安定にとっても脅威である。感染症は衛生設備が整っていない途上国の問題、自らが被害国になるはずはないという認識が先進国の多くにはあったのではないか。そのような意識を改め、国家安全保障の枠組みでも、水際対策や医療の指揮命令系統、ワクチンや医療用品の生産体制を見直す必要があることは言うまでもない。加えて、地域、グローバルなレベルにおいても、状況評価や医療用品・医薬品の供給網、緊急時の渡航に関する基準等、さまざまな側面から合意枠組みの見直しや制度の新設を検討するべきだろう。残念ながら、世界政府が存在しないこの国際社会において、何らかのルールや制度を作ったとしても、その有効性を保証するものは存在しない。だからこそ、複数のレベルで相互に補い合うことを目指す必要があるだろう。ウイルスとの闘いにまだ終わりが見えそうにないが、今回の教訓が建設的に生かされていくことを願うばかりである。
執筆者プロフィール
詫摩佳代(たくま・かよ)
東京都立大学法学部教授
東京大学法学部卒業、東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻修士課程終了、同博士課程単位取得退学。博士(学術)。専門は国際政治学、国際機構論。東京大学東洋文化研究所助教、首都大学東京法学政治学研究科准教授を経て現職。著書に『国際政治のなかの国際保健事業』(ミネルヴァ書房、2014)、『人類と病ー国際政治から見る感染症と健康格差』(中公新書、2020)、分担執筆に『新しい地政学』(東洋経済新報社、2020)、『グローバル保健ガバナンス』(ミネルヴァ書房、2020)、『新型コロナ対応・民間臨時調査会 調査・検証報告書』(ディスカバリー、2020)など。