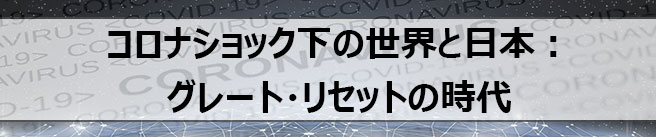コロナショック下の世界と日本:グレート・リセットの時代 (12) 新型コロナ危機と四つのアメリカ 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 中山 俊宏【2021/7/21】
掲載日:2021年7月21日
慶應義塾大学 総合政策学部 教授
中山 俊宏
2020年3月、アメリカにおいて新型コロナ危機が発生すると、事態は信じられないようなペースで悪化していった。それまで深刻な被害を受けていた中国、イタリア、そしてスペインをはるかに超える勢いで、罹患者数が増え、また死者の数も増大していった。パンデミックの波に襲われるニューヨークの光景に世界が愕然としたことは記憶に新しい。こうした状況、さらにその状況を正確に認識しようとはしない大統領、またパンデミックそのものが政治化され、科学的知見にもとづいて対処される事案ではなく、党派論争の対象になってしまったアメリカの現状は、多くの人に「迷走するアメリカ」の印象を強く植えつけた。
しかも、その「迷走」は、一時的なものではなく、より本質的なものではないか、そう多くの人が感じていたはずだ。アメリカの「衰退」については、もう大分前から、語られていた。ファリード・ザカリアが『アメリカ後の世界(The Post-American World)』を著したのが、2008年。2008年は、対テロ戦争の迷走がはっきりと認識されるようになり、リーマン・ショックが発生した年だ。まさにアメリカの「衰退」が可視化された年だともいえる。
しかし、『アメリカ後の世界』は、そのタイトルに比して、中味はそれほど暗くはない。というのも、ここでザカリアが論じているのは、主として「その他の台頭(the rise of the others)」についてであって、アメリカの「没落」ではないからである。要は、BRICsを筆頭に多くの国が、アメリカが構築した世界システムの中で台頭しつつあり、それがアメリカの相対的衰退を現象面で引き起こしてはいるものの、それはアメリカの没落ではなく、むしろアメリカの成功の結果だというニュアンスさえある「明るい衰退論」だったからだ。
しかし、新型コロナ危機を受けて、多くの人が感じるに至った「衰退論」には、こうした「明るさ」はなく、もはやわれわれが知っているアメリカは存在しないのではないかというアメリカに対する根源的な疑念のようなものが影を落としていた。21世紀に入ってからのアメリカが外の世界に投射してきたイメージは控えめにいっても褒められたものではない。1990年代のアメリカは冷戦の勝利を謳歌し、単極時代の余裕を味わっていた。しかし、21世紀に入ると、9.11テロ攻撃への過剰反応、格差の更なる増大、リーマン・ショック、オバマという「希望」の挫折、そしてトランプの誕生など、アメリカ人の自己イメージがどうであれ、とても「世界の最後の希望(last best hope of earth)」(リンカーン)と胸を張って言える状況ではなくなっていた。
新型コロナ危機への対応の不味さは、「衰退論」を決定づけてしまうのではとの不安を多くの人が感じていたに違いない。背景にトランプ大統領の声が響いていたことも、そうした不安を加速させたことは間違いないだろう。しかし、2021年に入ってからは、ワクチン接種のスピードと規模で他の多くの国を圧倒し、アメリカの底力を見せつけたかのように見えた。トランプ政権下で進められたワクチン開発、そしてそれをバイデン政権下で効率的に人々に届けたことは、「いざとなればできるアメリカ」の印象をどうにか提示することができた。しかも、アメリカの経済指標はインフレの懸念はあるものの好調だ。2021年1月に発足したバイデン政権は「アメリカが戻ってきた」とのメッセージを、ことあるごとに訴えている。
衰退論は、一時的に押し返したかのように見える。たしかにバイデン政権の誕生は、「普通のアメリカ」が戻ってきたとの印象を植えつけてはいる。しかし、問題は、他の国との関係においてアメリカが衰退しているかどうかではなく、アメリカ自身が内在的に直面している状況である。アメリカにおける分断状況はコロナ禍によってむしろ加速し、表面的な落ち着きとは裏腹に、それはアメリカの政体を奥深くから侵食する病巣のように広がっている。ジョージ・パッカーは新著『ラスト・ベスト・ホープ(Last Best Hope)』(2021年)において、アメリカにおける分断を新たな視点から類型化している。それは、保守とリベラルというシンプルな二項対立ではなく、人々の怒りや不満、そして絶望や敵意が複雑に絡まり合い、共同体を成立させるストーリーを深く侵食するような分断である。保守とリベラルの対立は、共同体を構成する異なるストーリーをめぐる対立だった。しかし、パッカーの描き出す状況は、このストーリー自体が成立しえない分断状況だ。
パッカーは、それぞれ交差することのない「四つのアメリカ」について語っている。その四つのアメリカは、概ね保守とリベラルの対立に吸収されていくが、それは保守とリベラルの対立の構図を強化するというよりかは、その対立自体を無意味なものにし、それぞれの陣営内部の亀裂の方をより深刻な分断として扱っている感もある。つまり、これまでは二大政党と概ね重なるかたちで整序されていたイデオロギー対立が、そうではなくなり、より複雑な様相を呈していく可能性を示唆している。
四つのアメリカとは以下のようなものだ。まずはリバタリアン、つまり「小さな政府」の原則に突き動かされる「フリー・アメリカ(free America)」がある。これは、レーガンによって体現されるが、冷戦の終焉とともに、「フリー(自由)」の意味が変化し、共産主義との対峙という意味合いは希薄化していき、もともとあった連邦政府の介入からの自由という方向に大きく傾いてしまっている。それは、「放っておいてくれ」という衝動に突き動かされる、「消極的自由」の原理的な追求に堕してしまった感がある。次に、アメリカで進展する変化に取り残され、ホワイト・クリスチャン・ナショナリズムに根を下ろす「リアル・アメリカ」がある。これは、2008年に共和党の副大統領候補だったサラ・ペイリンによって体現される。それは、アメリカが変わっていくことに対する敵意そのものが、政治運動化したようなものだ。そこには、人種主義、孤立主義、そしてナショナリズムと信仰心が綯い交ぜになったクリスチャン・ナショナリズムの影響が色濃い。トランプ現象は、この層に根を下ろしつつ、「フリー・アメリカ」を取り込んでいった。
リベラル派の方は、「スマート・アメリカ」と「ジャスト・アメリカ」に分断している。用語だけを見ると、ポジティブな意味合いを持つような印象を受けるが、パッカーの批判は厳しい。「スマート・アメリカ」は、アメリカの変化にもっとも馴染んでいるエリート大学卒の都市郊外に住むプロフェッショナル・クラスである。「スマート・アメリカ」はメリトクラシーの原則の下、競争を勝ち抜いてきた人たちによって構成されるが、もはやそれは「階級」の感をなし、「スマート・アメリカ」の外で育った子供たちが、このグループに入ることはますます難しくなっている。この層の最大の問題は、「スマート・アメリカ」の循環的再生産だ。しかし、競争を勝ち抜いてきただけに、自らの存在に対する正当性の感覚が強い。アイビー・リーグの大学の卒業証書が最重要の価値を持つようなグループだ。
そして、「ジャスト・アメリカ」は、特に若い世代、ミレニアル世代やZ世代によって構成され、これまでのアメリカン・ストーリーの中に居場所を見出せず、アメリカという成功体験を知らず、「スマート・アメリカ」にも参入できないグループで、「ジャスティス(正義)」を軸にアメリカの罪を告発していく層だ。「オバマという希望」が未完に終わった後、急進化し、白人警官によるアフリカ系アメリカ人に対する暴力の告発をきっかけに勢いを獲得した。そこに、ジェンダー、気候変動、格差問題なども重なり、その主張の「正しさ」ゆえに、「不寛容な正義」という方向に向かいやすい。トランプがそうした傾向を加速させたのはいうまでもない。トランプの存在が、彼らの「正しさ」を確信させたという構図だ。彼らの告発は、「フリー・アメリカ」と「リアル・アメリカ」に対して向けられるが、「スマート・アメリカ」に対しても手厳しい。
こうした分類は、恣意的なもので、あくまで類型に過ぎない。当然、単純化の謗りを免れえないが、リベラルと保守という分類では捉えきれない、分断の複雑な様相を捕捉している。この四つのアメリカは、それぞれ異なった「新型コロナ危機体験」をした。新型コロナ危機を歴史上の他のどの危機と比較していいのかは難しいところだが、アメリカ全土を覆った危機であったことは間違いない。
アメリカは、日本のように国に対する感覚が、歴史的・文化的・言語的連続性の上に成立している国家ではない。アメリカは、肩越しに後ろを振り返っても、誰もが共有できる「足跡」を確認できない国家であり、さらに分断と対立が潜在的には国家の本質でさえある。それをどうにか「多様性」というかたちでまとめ上げているに過ぎない。過去に依拠することができない共同体であるアメリカは、将来に実現するであろう「パーフェクト・ユニオン」に自らの現在の姿を投射し、そちらの方向に向かって一緒に歩いていくということを通じて共同性を実現していく。それゆえに、アメリカという国は、この共同性をリアルなものにするために、「危機」を必要としている国であるという見方もできる。つまり、「アメリカという理念」を脅かす存在を現出させることによって、その理念をリアルなものにするという図式である。「アメリカが危ない!」という「危機のレトリック」は、アメリカという存在をリアルなものするために必要不可欠なものであるとさえいえる。アメリカの分断(南北戦争)、ナチスドイツや大日本帝国との戦争(第二次世界大戦)、共産主義とのイデオロギー対立(冷戦)、9.11テロ攻撃と対テロ戦争と、アメリカは危機に対峙する中で、自らを確認してきた。
しかし、この危機がアメリカにとって意味があるものであるためには、それが「共通体験」でなければならない。しかし、新型コロナ危機は、四つのアメリカにとってそれぞれバラバラの体験であった。「フリー・アメリカ」にとって新型コロナ危機は、新型コロナ・ウィルスによって引き起こされた危機であるよりかは、むしろ「過剰な連邦政府の介入」を呼び込んだ危機であった。他の多くの国とは異なり、アメリカにおける「反ロックダウン」は、単なる「危機疲れ」ではなく、政治的な抗議表明だった。「リアル・アメリカ」の新型コロナ危機体験は、トランプの視線を通して体験された。当局によるマスク着用の推奨を、銃に対する規制と同じロジックで捉え抵抗、2020年の大統領選挙におけるトランプ大統領のイベントで、マスクを着用している人がいかに少なかったかを思い返せば、容易に想像がつくだろう。ワクチンの接種に抵抗する「アンチ・バクサー(anti-vaxxer)」もこのグループに多い。
「スマート・アメリカ」の住人は、快適なネット環境の下で、オンライン勤務をし、万が一罹患しても、他の層よりは恵まれた医療環境のもとで暮らしていた。そもそも、普段から「ヘルス・コンシャス」なこの層は、重篤化の危険性も相対的には低かった。「スマート・アメリカ」にとって、新型コロナ危機がなかったわけでは当然ない。個々で見れば、家族を失った人、学校に子供を通わすことができない状況を憂慮した人などがいることは間違いない。しかし、この層にとっての新型コロナ危機は、ただひたすら耐え忍ぶという体験だった。「ジャスト・アメリカ」は、また違った体験をした。ジャスト・アメリカは、マイノリティのアメリカでもある。アフリカ系やラティネクスが、新型コロナ危機によって他の人種グループと比して、深刻な被害を受けたことは繰り返し伝えられたところである。ジャスト・アメリカは、コロナ危機がトランプ政権期に起きたことで、より先鋭化した。それは、まさに彼らが主張するところの「システムに埋め込まれた差別」を顕在化させたと彼らが捉えたためだ。
こうして、新型コロナ危機という未曾有の危機でさえも、アメリカは共通の「体験」をすることができなかった。このことの意味は深刻だ。たしかに、ワクチンの接種が進み、バイデン政権の発足で、ことは沈静化したように見える。1月6日のMAGA反乱の喧騒は、遠い昔のことのようだ。しかし、新型コロナ危機下でも、アメリカが共有できる「ストーリー」の蘇生は果たせなかった。だとすると、この先、何がこれを実現することができるだろうか。いまのところ私にはそれが思い浮かばない。
執筆者プロフィール
中山 俊宏(なかやま・としひろ)
慶應義塾大学 総合政策学部 教授、日本国際問題研究所 上席客員研究員
青山学院大学国際政治経済学部卒業。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科博士課程修了、博士(国際政治学)を取得。ワシントンポスト紙極東総局記者、日本政府国連代表部専門調査員、日本国際問題研究所主任研究員、ブルッキングス研究所招聘客員研究員、津田塾大学学芸学部准教授、青山学院大学国際政治経済学部教授などを経て2014年より現職。2017年にはビクトリア大学ウェリントン戦略研究センター・サー・ハワード・キッペンバーガー・チェア客員教授、2018~19年にはウッドロウ・ウィルソン・センター・ジャパン・スカラー、2019~20年には防衛省参与。専門はアメリカ政治外交、日米関係、国際政治。著書に『アメリカン・イデオロギー』(勁草書房、2013年)、『介入するアメリカ: 理念国家の世界観』(勁草書房、2013年)など。第10回中曽根康弘奨励賞受賞。